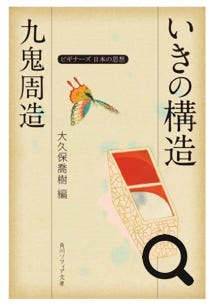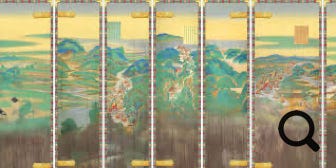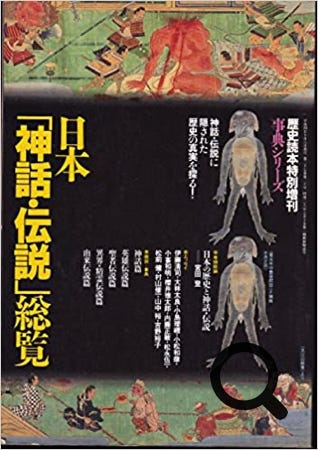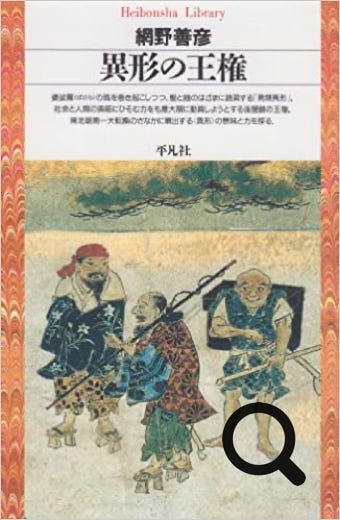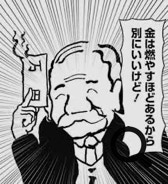3B 2022/04/27版
第3回 補足資料
テキストAと同じ内容の部分はグレイで表示しています。
↓
当講義の目的
3回に渡り、「日本美術における畏敬と異様の系譜—俗の芸術史」について講義を行います。第一回目は、中世、およそ奈良時代から室町時代の終わりまでについて。続く第二回目は、安土桃山時代から江戸の終わりにかけて発生した「日本美術史における俗—庶民の間に成立した芸術」について検証を行います。
美術は、ハイ・アートと、そうでないものとして、これまで論じられてきました。一方で日本の美術は仏教の伝来移行、常に宗教美術を中心に語られてきた。しかし、そのような従来通り歴史の古い方から、並べられた芸術の歴史ではなく、現在の我々の芸術、ポップアートやポップ・カルチャー、とりわけマンガや、アニメや、ユース・カルチャーなど、身近に横たわっている美術や、作品から、日本の美術を逆挽き的に眺めてみると、かなり異なる芸術の歴史や、影響が見えてきます。
たとえば、現代のAKBなどのガールズ・ユニットや、イケメンのアイドル・ユニットが、歌舞伎の創生期を彩った女郎歌舞伎や、野郎歌舞伎と、よく似た性質を持っていたり、マンガの表現で、背景に描かれる炎が、仏像の光背と等しく、闘神像の髪形である怒髪天が、無敵となった変身ヒーローの髪形として採用されているなどが、その一例です。
これらの例が示すように、現代の芸術やメディア的表象(イメージ)に影響を与えた日本の芸術、文化、風習を読み直していくことから、日本のメディア芸術の歴史を再構成していくのが本講座の目的です。
中世から江戸末期までを扱う講義に続く、6/17㈬の第3回めの講義では、鎖国が説かれ西洋文化が押し寄せてきた、明治期から現代までを論考します。
そのほとんどは昭和の時代の俗カルチャーと文化的変遷についての論考です。皇国として戦争を闘い、敗戦後、民主化とアメリカ西洋文化の洗礼を受け、さらに高度成長期を越えていった昭和の時代に、どのように現代的日本の文化、芸術が成立したのか、あるいはそれまでの歴史と分断されていったのかについて検証を行います。
講義のタイトルは、「ヤンキー芸術論」と命名しています。
ヤンキーという言葉をあえてタイトルに使用するのは、本講義が試みる我々の時代の俗芸術を紐解く上で、もっとも日本的なもの、あるいは日本的文化の根本的な姿勢、普遍的な日本の俗芸術の活動が、この「ヤンキー」という言葉に集約されていると考えるからです。
そのような思考の中では、オタクや、カワイイや、ギャルも、広義的にヤンキーという概念に内包されます。それはオタクVSヤンキーや、普通VSヤンキーとして括られる素行の悪い連中といった、対峙する概念ではなく、日本文化の総体をヤンキーという「俗」の概念で読みとする試みが、本講義の目的だからです。
日本の芸術史、ヤンキー、たしかにヤンキーは怖い。でもそういう訳で、この「怖い物」を全体テーマに掲げる、この授業に含めているだけではありません。詳細はのちに論じますが、日本の美術や、仏教の美術、または「俗」の語に集約される、日本の美術の根底には、恐れを表そうとする意識、または怖さを模倣する意識が、通底していると考えています。そのような「畏怖畏敬の俗の美学」そのものが、怖さと深く繋がっているからです。
そのような中世と近代に栄えた俗の芸術が、再び開花したのが、アメリカとの戦争に敗戦してからバブルの時代までという昭和の時代でした。1950〜1990年代という年代です。この昭和のヤンキー的美意識は平成へと受け継がれて、さらにカワイイやなど、様々な俗の美意識へと転化されていきました。この美意識はいまも、我々が生きるこの時代の「日本の芸術文化」の根底に鎮座しています。
当講義では、そのような歴史的に関連性を語られて来なかった、「日本の古層」から、現代へと通底し続けている、日本文化における、畏敬と異類の芸術の系譜を、もう一つの日本のメディア芸術として論考していきます。
不動明王像の光背は炎
現在のマンガにおける背景と
共通の関連性をもつ
ヤンキーとは特別な人々ではなく、純度の高い日本文化の継承者だ。(次回説明)

はじめに ☆須佐之男命の神話からアニメの世紀へ
テキストAと同じ内容なのでグレイで表示しています。
↓
永く他の文明と接する機会がない孤立した文化では、技術や思想の多面的進化がおこらないまま、文化の促進が停滞すると考えられるが、その一方で伝統的技術や思想が洗練されていく。(*参照:加藤周一「日本その心と形」P24)
日本に流入した大陸文化で、決定的な影響を与えたのは、水稲技術と米の栽培、金属器の導入―銅剣、矛(ほこ)と、のちに神器として用いられる銅鏡の製造)、そして仏教の伝来、鉄砲と火薬、さらに黒船による開国であろう。本書ではこれに第二次世界大戦の敗戦によりもたらされたアメリカ式民主主義と生活スタイルの変化を含める。
縄文の時代から現代に至るまで、日本は極東にある閉鎖された島国という地勢により、孤立、あるいは海外文化の影響を最小限に留めるようにして、得意な文化を創り出してきた。それを洗練と呼ぶか奇抜と呼ぶかはさておき、独特の文化を形成してきたというのは疑いようがない。異文化の技術や思想は日本独特の捉え方で、アレンジされていった。
青銅器の例で言うと、もともと鋭利な武器として使う目的で細く作られていた銅剣は日本では幅広で長いものとして作られるようになった。武器であるよりも権力の象徴的役割を担うようデザインを変えたのだ。鏡は神道の神具として祭礼で使われ、のちにご神体となって神社に置かれた。その後、剣と、玉と、鏡は天皇家の象徴とされた。仏教も、それまで信仰されていた古来の宗教と習合して日本独自の信仰となった。(※参照:加藤周一「日本その心と形」P32)
日本の独自性とは、モンスーンの風土や、極東という地勢的条件だけでなく、その得意な文化状況により成立していった。すなわちたぐいまれな物事をすべて日本的にアレンジしてしまうか、日本的に適合させてしまう日本的気質によるところが大きいのではないだろうか。はガラパゴスと揶揄される状況もあるが、そうであったとしても、この日本的な独特の文化の生成こそ、文化、しいては日本の芸術の特徴といってよいであろう。
そして日本ほど庶民の文化が脈々と受け継がれ、後生に受け継がれていった文化はない。アジアの大陸の国々、あるいは西洋のキリスト教社会や、インドなどのヒンドゥー教の国々、中東を中心とするイスラーム教の国々、または中国など大陸の仏教国と比べて、貴族、王族、武士といった支配者階級の文化はあるが、それと並んで浮世絵や歌舞伎などの庶民の文化や芸術が、日本では成立した。 錦絵、浮世絵、着物の柄、または歌舞伎に代表される日本の芸術と芸能とは、庶民文化で開花した。
・怖い
それら日本の芸術には、独特の怖さがある。その怖さとは、力に対する信仰・崇拝であったり、自己を同化習合させようとする意識が読み取れたり、他者への威嚇であり、さらには六道絵や地獄絵のように怖れ不安がる気持ちが表した芸術である。
庶民だけでなく永く戦国の時代が続いたこの国では、皇族や貴族という支配階級とは別に、サムライというもうとつの武闘派勢力が、長期にわたって国を支配していた。
サムライが台頭した鎌倉、室町の時代、戦国時代、安土・桃山と江戸の時代にかけて、彼らは独特の怖さを自分に引き寄せるような意識が成立させ、兜や、刀、または武士道しかり、怒りのデザインといっていいような芸術と思考を熟成させた。
・畏敬と畏怖の日本美術
おもてなしなどという、後付された美学だけが、この国の美学ではない。
「いき」や、「婆娑羅」など、古い日本の芸術は、思う以上に怖さを讃えている。
神道は荒ぶる神々を祭り、表してきた。これほど怖い神々や表象を量産し続けている文化は他にないのではないか。
それは過去の話ではない、日本のアニメやマンガ、またはファッションや、芸能のジャンルでも同様の怖さの表象が繰り返されていく。実例をあげる
これから、怖さの表象―畏敬と畏怖を主軸として、日本の美術史を読み直し論考を行う。それらの関連性を指摘する。中世の仏像や、百鬼夜行や鬼といった民間伝承の奇談や、武家社会の信仰、鎧兜の威嚇のデザインや、江戸の庶民の風俗や大和絵・浮世絵・歌舞伎等を経由して、現代のアニメやマンガ、ヤンキーやオタク文化への波及と流用を調査するものである。(※参照:加藤周一「日本その心と形」P49)
日本の奢れる庶民美術のルーツを辿れば、中世に成立した風流の美意識、あるいは、あえて「風流」(現代の風流の意味とは異なる)の芸術運動と呼ぶべき、民俗活動。
歌舞伎の語源となったかぶき者、あるいは数奇者、かぶくという意識として集約される。
戦国時代から江戸初期におきた、庶民、とりわけ一般庶民の若者たちの間に蔓延した、ニヒリズム、刹那主義。
さらに明治期から積み重ねられていた抑圧的な帝国主義思想の果ての第二次世界大戦の敗戦によって、日本の帝国主義が崩壊したとたんに、積を切るように押し寄せてきた、敗戦後のアメリカ文化の影響。
それらが重要な要素であると考える。(このアメリカ文化の到来を筆者はこれを第二の開国と呼ぶ。)
昭和の戦後以降から始まる、いわゆる高度成長期における様々な要因も、同じく、本講が取り上げる庶民の芸術、とりわけ若者の美術に多大な影響を及ぼしている。
昭和の時代の、モータリゼーション、都市化、および郊外文化の誕生とともに、戦後期になってから「若者」という概念が書き換えられ、変化した。
そしてコンビニ店舗やドンキホーテ、ラジオの深夜放送といった夜の誕生によって、戦前までの日本の思想や美意識が塗り替えられ、熟成されていった。
昭和の時代とは、それまでの日本の庶民文化を蘇生させ熟成させていったが、その一方で決定的に本来の日本的なものとは異なるものとして、読み替えが行われた時代であった。それは古き文化の喪失ではなく、ヴァージョンアップ、または、読み替えであった。
本講義の前半は、今日の日本の美意識や創造の、根源的な感性や構造を形成した「中世」と、戦国時代以降から江戸の終わり―世界的にも類をみない庶民文化を成立させた「近代」までを2回に分けて紐解く。そして後半で明治から大正と昭和の時代を第二次世界大戦前と戦後から昭和が終わりまでの「現代」という3つの時代に区分けして検証する。
・中世—仏教と穢土、庶民の不安と恐れが創造した美術 〜40000文字
A 密教の尊格と闘神の表象
A-1 仏教伝来とその後の日本の美術
・仏教の伝来
仏教が日本に渡来したのは六世紀中頃(飛鳥時代)と推定される。朝鮮半島から伝わった仏教が日本の宮廷に伝わり、やがて七世紀の早い時期に、聖徳太子(厩戸皇子 ルビ:うまやどのおうじ 574?~622年)によって、仏教は国教として推進された。
仏教は約2500年前(紀元前5世紀)にインド北部ガンジス川中流域で、釈迦によって提唱されて始まった。その後紀元前3世紀にインド初の統一国家となったマウリヤ朝による保護の下でインド全域に広がった。仏教は西北インドから中央アジアを経由して、シルクロードを東進して、紀元1世紀に中国へと伝播した。その後四世紀に朝鮮半島を経由して、日本に伝来した。
・神仏習合
極東の閉ざされた島国ゆえ、文化を温存する性質をもっていた日本は、その反面、外界から影響で大きな変化がもたらされてきた。日本は外界からの影響によって、その文化、政治の進路を大きく変えてきた。
仏教は、それまで崇拝されていた日本の土着的神々と習合し、あるいは日本的土壌の影響を受け、日本的な信仰として変容した。プリミティブな宗教や土着的文化も、ただ消えるだけではなく、仏教と習合して、新たな宗教や文化へと変わりながら存続していった。日本古来のアニミズム的宗教は表象的イメージ(偶像)や教義、社を持つものではなかった。神の存在は元々不可視なもので、依り代によって知ることのできるものとされてきた。しかし仏教が伝わると、その影響によって、神像の造形によって神の存在が表現するようになった。神話や教義が作られた。神社の建造が行われるようになったのもこの時期と推測される。(※参照:加藤周一『日本その心と形』P52)
・飛鳥時代―静的で単純明快な仏像
日本にはそれまで本格的な造像の技術はなかったが、仏教とともに大陸の本格的な造像表現と技法が持ち込まれた。それゆえゆ、仏教の伝来とは、造形技術の到来であり、芸術の伝来に等しい。
飛鳥および白鳳(ルビ:はくほう〉時代の仏像を代表する仏像のひとつ法隆寺金堂釈迦三尊像(図*)には、実在する人物を感じさせるようなディテールやリアルさはない。謹直な姿勢で正面を向いている像で、均等がとれていて、左右対称のシンメトリーの形状である。面長な顔をしていて、身に付けている布は永く垂れて、魚のひれ状に広がっている。抽象的で、象徴としての神像という、神秘性と、スマートさを印象付ける。
これらの仏像は大陸(南北朝時代の中国)で作られ、持ち込まれた東寺の仏像の作風と共通性を伺わせるが、一方で日本的な仏像への解釈が加えられていて、大陸のものよりもより単純化されていて、抽象の度合いが強く、静的な印象である。これらの仏像からは、古墳時代の埴輪(ルビ:はにわ)と同じような、やわらかくて朗らかな表情が伺える。長身で、手足が長く、しなやかな身体の形状もそうだが、全体的に単純明快である。そこからは静的なものをなによりも優先する美意識が感じられる。
・奈良時代―絢爛豪華なコピー文化
都が平城に遷された和銅(ルビ:わどう)3年(710年)から、延暦(るび:えんりゃく)13年(794年)まで続いた奈良時代、あるいは美術史において天平と呼ばれる時代(729~749年)は、飛鳥・白鳳の時代と同様で、中国(唐)の強力な影響下に文化全般がおかれていた。富と権力を背景とした華やかな貴族階級の文化が繰り広げられていて、遣唐使の派遣によって多くの人々が唐に渡った時代で、従来から名乗ってきた国名の「倭」(ルビ:わ)を改め、中国に対して「日本」の国号をたてたのがこの時代であった。
当時の唐は中国全土を統一して、シルクロードの国々にも支配を及ぼしていた。西アジアや北アフリカ(中東)のイスラー ム教の国々、そして文化・宗教思想と同じく、芸術においても高度な発展を遂げていた当時のインドとも深く結びついていた。それゆえ、この時代の中国は、国際性に富み、それらの国々の文化を融合しながら、それにアレンジを施したような独特の文化を成立させていた。
公益から得られた膨大な富によって潤う長安(現在の陝西省西安市)の都には、豪奢(ルビ:ごうしゃ)な貴族文化がはなひらいていて、高度な技術で創造された芸術作品が、次々と奈良へと持ち込まれた。別な言い方をすると、この時代の奈良の都とは、長安の貴族文化を奈良に再現しようとしたものであった。建築・絵画・彫刻・文献・工芸、すべての分野で、奈良の大仏殿(東大寺盧舎那仏像(ルビ:とうだいじるしゃなぶつぞう))に代表されるような大規模な建造物や、豪華な造営が、国家の予算を使って促進をされていた。
この時代に作られた仏像における中国、そしてインドの影響をいくつか紹介する。681年に天武天皇が藤原京に建造を始めた薬師寺の伽藍(ルビ:がらん、主要建物群)は697年に完了している。現存する「薬師如来像」と、脇待の二体「日光菩薩」と「月光菩薩」からなる三仏(*図)は、もともと光背(ルビ:こうはい)だけでなく、仏像までが全身金色で、当時の唐の仏像様式の類型とみなされる。そうでありながら、この仏像からは古代インドのグブタ朝などからの影響が伺える。台座に彫り込まれた特徴的な羅刹鬼(ルビ:らせつき)も、インドのもので、葡萄唐草の文様はより西方のアジアに由来している。このように国際的な影響下で成立していた唐の仏像芸術の影響が、奈良時代の仏像に垣間できる。簡単に言ってしまうと、奈良時代の仏像とは、中国から輸入された仏像か、その複製品といった感がゆがめないものが少なくない。(※参照:『日本美術の歴史』P64)
A-2 威嚇する仏像 —中国、インドの影響
・密教―インドから伝播した密教における怒りの表象と畏怖の美術
密教とは大乗仏教の最終段階に登場した仏教における秘教のひとつ秘密仏教である。神秘主義的な性質を多分にもち、呪術的で、象徴的なイコンをもつ特徴をもつ。ヒンドゥ教と同じく、シヴァ神妃になぞらえられた女性的力動の概念シャクティ(性力)の教義を説く古代インドのタントリズムの精神や文化と深い関連性を持つ。(※参照:辻惟雄『日本美術の歴史』P87)
密教は大乗仏教の一つの流れとしてインドで始まった。七世紀から八世紀にインドの真ん中から南インドの地帯で隆盛したが、その後のイスラーム教の侵入を要因として一三世紀初頭頃にインドで消滅した。(※参照:松永有慶『密教』P5)
中国で栄えたのは七世紀から九世紀初頭で、随から唐の中頃までの期間であったが、清代以降に禅や浄土教、道教の台頭によって衰退して、途絶した。それまでの仏教と異なる様々な体験を課す教えが中国では根付かなかったのも衰退の理由とされる。
スリランカやインドネシアなどの東南アジアの国々でもインドから直接伝播して栄えたが、これらの土地でも同じように衰亡した。
チベットは七世紀頃にインドと中国の両方から仏教が伝えられ栄えたが衰退してしまった。11世紀になって再びインドで学んだ僧によって再興され、西チベットを中心とした、仏教の復興運動がおきた。その後密教がチベット全域で信仰されるようになった。
現在でも密教が一般庶民によって信仰され、僧侶たちによって促進されているのは、日本とチベットだけである。(※参照:松永有慶『密教』P6)
・密教の伝播
九世紀初頭の中国に留学した空海は804年に中国長安で密教の秘法を学んだ。大同元年(806年)に帰国して、京都高雄山寺(ルビ:たかおさんじ)(現在の護国寺)(ルビ:ごこくじ)を拠点として、高野山金剛峯寺(ルビ:こんごうぶじ)や、京都東寺(ルビ:とうじ)に密教の伽藍(ルビ:がらん)を創設した。
日本の密教におけるもうひとりの立役者として知られる最澄(ルビ:さいちょう)(766/767年 - 822年)は、804年に唐に渡り、翌805年に帰国して、自ら創設した比叡山延暦寺(ルビ:えんりゃくじ)を拠点として天台宗の開祖となった。空海と最澄だけでなく、後に唐に渡った後発の僧侶たちも日本の密教の布教に尽力した。
空海が中国から持ち帰った法具には、数々の経典(経論(ルビ:きょうろん)―教えを記した経と、経の注釈書)とともに、曼荼羅(ルビ:まんだら)や、祖師の画像など多くの絵画が含まれていた。それまで立体の仏像を主な崇拝の対象としてきた日本の仏教は、これ以降から、絵画(仏画)が崇拝の対象として扱われるようになり、後の仏教美術における絵画の重要性を決定的なものとした。(※参照:辻惟雄『日本美術の歴史』P87)
それまでの仏教が文字で記述された経典などから教えを得たのに対し、密教では根本経典の一つ『大日経』に標された瞑想などの呪法が重んじられた。体得である。さらに曼荼羅や法具類、儀式を伴う「印信」や「三昧耶形(ルビ:さんまやぎょう)」など象徴的なもの、法具などのシンボル的なものが崇拝の対象とされた。
空海が伝えた純密の思想では、大日如来を中心に据え、密教的世界観を図表した曼荼羅を拝した教義と実践法を重要と考える。六世紀の終わり頃になると共同体の祭祀を中心に据えた従来の神祇信仰は行き詰まりを見せ始めていて、豪族・貴族個人の新たな精神的支柱が求められるようになっていた。大乗仏教は、仏に絶対的に帰依し,自らの仏性を認め,それを体現することを目的として、他人に対する善い行いをすることが重要だとするが、密教が推奨する、なにかしらの行為で御利益が得られるという教義は、広く豪族たち支配者階級に受け入れられた。なにより象徴的で能動的な行為を尊ぶ純密の教えは、宮廷や貴族階級から熱烈に支持を集めたのだ。また、密教はもともと日本にあった山岳信仰や修験道などの宗教とも親和性があり、独自の神仏習合が促進されていった。
・インド バラモン教の影響
不動明王などの尊格を安置し、護摩壇(ルビ:ごまだん)で護摩木を燃やしながら祈禱する護摩(ルビ:ごま)の儀式をはじめ、密教では多くの儀礼・儀式が行われる。護摩がインドの宗教において供物や犠牲、いけにえを意味するサンスクリットのホーマ(homa)の音訳であるように、密教の儀礼はバラモン教などインド系の宗教にルー ツをもつ。寺院に祀られる明王像や四天王の天部(ルビ:てんぶ)の仏像は、多面多臂(ルビ: ためんたひ)(顔と腕が多い)像や、忿怒(ルビ:ふんぬ)(激昂(ルビ:げきこう)した表情)のものが多く、それらの偶像は、バラモン教、さらに、インド・ヒンドゥー教と深い関わりや密接な繋がりを思わせる。
密教の経典には、他の仏教とは異なる呪術的な要素が散見される。六世紀頃に成立したとされる経典は、そのほとんどが呪法を標す内容で、日本ではそれを雑密(ルビ:ぞうみつ)経典と呼んだ。これに対して『大日経』(ルビ:だいにちきょう)と『金剛頂経』(ルビ:こんごうちょうきょう)が標されたのが純密(ルビ:じゅんみつ)経典と呼ばれるもので、七世紀には両方共ともにある程度の完成した経典として成立していたと思われる。(※参照:松永有慶『密教』P21)
密教の仏像・尊格の多くは怒りを表す。それらは魔障(ルビ:ましょう)(仏道の修行を妨げる悪魔の障害)を降伏させようとする意匠であり、その威嚇するような図像と彫像は、ヒンドゥー教を代表とする仏教以外の宗教から取り込まれたイメージである。(※参照:成田山新勝寺・種智院大学密教学会『総覧不動明王』P120)
これらの恫喝(ルビ:どうかつ)的な様相は、密教の仏像だけでなく、奈良時代から少なからず散見されていた。唐の様式の強い影響が見受けられる「八部衆像 阿修羅」(*図)(天平6年(734年)奈良興福寺)や、引き締まった肢体と、見開いた目と怒りの表情から力強さと迫力を感じさせる「執金剛神像」(ルビ:しつこんごうしんぞう)(*図)(8世紀前半、奈良、東大寺、法華堂)にも、密教仏につながるような傾向が伺えた。(※参照『日本美術史』P42)同じく「十二神将像 因達羅」(8世紀前半、奈良、新薬師寺)や、「四天王像 増長天」(*図)(8世紀前半、奈良、東大寺戒壇院(ルビ:かんだんいん))も同じく写実的な表現で、リアルで、実在する人物として存在しているような戦神・戦将の姿として表されている。これらの彫像はともに極彩色の彩色と切金文様がほどこされていて、作風に違いはあるが、密教伝来以前のインドの表象が中国を経由して日本にもちこまれていたことを伺わせる。
(註釈:本稿は密教における仏教美術の説明よりも、不動明王という畏敬のイメージについて論じるものであるため、日本の密教美術における重要な存在である「曼荼羅」図や、それ以外の密教の美術に関する説明や言及は行わない。)
・四天王と十二神将像
不動明王を含む五大明王(*図)、降三世明王(ルビ:ごうざんぜみょうおう)、軍荼利明王(ルビ:ぐんだりみょうおう)、大威徳明王(ルビ:だいいとくみょうおう)、金剛夜叉明王(ルビ:こんごうやしゃみょうおう)、または持国天(ルビ:じこくてん)、増長天(ルビ:ぞうちょうてん)、広目天(ルビ:こうもくてん)、多聞天(ルビ:たもんてん)の四天王も、明王と同じく憤怒の表情で、眼光厳しく、動感にみちた表現が常とされる仏神である。
仏の住む世界を支える須弥山(ルビ:しゅみせん)の四方向を護る四天王にはそれぞれが守護する方角と持ち物が決められている。東方を守る守護神である持国天は別の名が提頭頼吒(ルビ:だいずらた)で、三昧耶形(ルビ:さんまやぎょう、仏尊を 表す象徴)は刀である。増長天こと毘楼勒叉(ルビ:(びるろくしゃ)は南を守護し、刀剣と戟(ルビ:げき)とを持っている。西方を守護する広目天の梵名はヴィルーパークシャで、サンスクリット語で「種々の眼をした者」または「不格好な眼をした者」という意味で、特殊な力を持った眼をもつ天部の仏神とされる。別名は毘楼博叉(ルビ:びるばくしゃ)で、三昧耶形は三鈷の戟である。四天王で多聞天(*図)とされる毘沙門天(ルビ:びしゃもんてん)は、北方向を守護する。仏敵を打ち据える護法の棍棒を三昧耶形として持つ姿が一般的である。その多くは革製の甲冑を身に着けた唐代の武将風風に表され、邪鬼と呼ばれる鬼形の者を踏みつけている姿が多い。毘沙門天は独尊として広くアジアで信仰の対象されてきた武神で、室町時代末期からは日本独自の信仰である七福神の一尊とされている。さらに江戸時代以降は勝負事に利益を与えてくれる仏神として崇められてきた。
十二神将像(註釈)(ルビ:じゅうにてん)も、四天王と同様の天部の神々で、同様に甲冑を着けた武将の姿で表されてきた。十二夜叉大将、十二神明王(じゅうにやしゃたいしょう/しんみょうおう)ともいう。密教では十二神将像も四天王とともに重視されてきた。十二神将像は薬師如来(ルビ:やくしにょらい)と薬師経を信仰する者を守護する武神とされる。中国では十二支と結び付けて信仰されていて、敦煌の壁画にも作例が見られる。表情やポーズなどで個別の性質を表した彫像が多い。
奈良の新薬師寺におかれた十二神将像の素描が八世紀(奈良時代)に作られた国内最古の作例とされ、一般的にも知名度が高い。なかでもの伐折羅(ルビ:ばさら)大将像は日本の500円切手(*図)のデザインに使用されていて、もっともよく知られている塑像であろう。
「伐折羅」(ルビ:ばさら)とは、もともとサンスクリット語でダイヤモンド(金剛石)を意味する言葉である。密教の金剛曼荼羅や金剛力士像に用いられる金剛とは、究極的なもの、想像も及ばないもの、絶対的なものを表す言葉として使われていた。本書で後述する南北朝の動乱期の美意識や価値観として使われた流行語の「婆娑羅」という華美な服装で飾りたてた伊達(だて)な風体や勝手気ままなふるまいなどを表す言葉も、このサンスクリット語の「バサラ」を源流としているという説がある。他の十二神将像と同様に、伐折羅像も憤怒の表情をしていて、怒髪天(ルビ:どはつてん)と呼ばれる髪の毛が逆立つくらいの激しい怒りを表す髪型と形相が描かれている。これもマンガ「ドラゴンボール」における強さの表象などに繋がる。
・明王像
明王像も多面多臂の怪異な姿で描かれたものが多い。明王とは密教における尊格及び称号で、仏が説いた真言、呪文のことを指す。密教における最高仏尊大日如来の命を受けて未だ仏教に帰依しない民衆を帰依させようとする役割を担った仏尊を指す。あるいは如来そのものの分身が明王像だとされる。
インド・摩伽陀国(るび:まがだこく)の国王で、訳経僧であった善無畏(ルビ:ぜんむい)は、中国密教で三蔵法師の一人とされ、「善無畏三蔵」(ルビ:ぜんむいさんぞう)と尊称される善無畏(ルビ:ぜんむい)が、インドから中国にもたらした図像が明王像の原型となったと推測される。
・不動明王
尊格のひとつ「不動明王」は大日如来の化身とされ、アジアの仏教圏の中でも特に日本において根強い信仰を得ている。不動明王は五大明王の一員で、降三世明王、軍荼利明王、大威徳明王、金剛夜叉明王と共に祀られてきた。天台宗、禅宗、日蓮宗などの諸派では不動明王が本尊とされる。真言宗では大日如来の脇侍として祀られる。山にこもって修行を行うことで悟りを得ようとする日本古来の山岳信仰が仏教に習合した修験道でも不動明王が信仰されている。
不動明王もインド仏教においてどのようにして尊格となったのかあきらかでない。ただし不動明王も仏教本来のものではなくヒンドゥー教由来の偶像であることは、他の仏像とは異なる様態から想像できる。阿遮羅(Acala)という 梵名(ルビ:ぼんめい)(インドで使用されるブラーフミー系文字の漢訳名)から、類似する梵名をもつヒンドゥー教の「破壊/再生」を司る神シヴァと関係性があるだろうと推測される。(※参照:成田山新勝寺・種智院大学密教学会『総覧不動明王』P119)
その尊格は、もともとはインドの神々が仏教に取り込まれていく過程で成立し、おもに密教の尊格として伝わったと捉えるのが妥当であろう。そして日本に伝わったあとに山岳信仰や、神道の崇拝が混ざり合い、独自に発展していったイメージでもあった。
不動明王とはどのような尊格なのか。
盤石の上に安坐し、剣と羂索(ルビ:けんさく)を持って座った童子形の不動明王、その目は一目をして諦観(ルビ:ていかん)するがごとき形で唇をかみ、額にしわをよせ、頂髪は左肩に垂れ下がっている姿である。その背後には猛焰(ルビ:もうえん)が燃えさかっている。(※引用:成田山新勝寺・種智院大学密教学会『総覧不動明王』P120)
様々な亜流形状はあるが、多くの不動明王は、一面二臂という人と変わらない肢体をもち、片手には三鈷剣(ルビ:さんこつけん)を持つ。三鈷剣はインド由来の祭神具の一つで魔を退散させると同時に人々の煩悩や因縁を断ち切るものとされている。三鈷剣には倶利伽羅竜(ルビ:くりから)が巻き付いている場合があり、そのため「倶利伽羅剣」と呼ばれる。
もう一方の手には羂索(ルビ:けんさく)と呼ばれる投げ縄のようなものも持っている。羂索は悪を縛り上げるための縄であり、煩悩から抜け出せない人々を縛って吊り下げてでも救い出すために用いられる縄だといわれる。
身体は青黒い色で表現されたものが多く、筋肉質で、屈強な印象が強い。どちらかというと肥満気味な体つきをしている。身に付けている衣装は古くは赤土色が定番であったが、現代では青色も散見される。片方の肩にぶら下げられた布で下半身が覆われている。そのような着衣のため厚い胸元と太く筋肉質な腕があらわに見て取れる。腕輪や首飾りなど重そうな装具を付けた像も少なくない。
頂(髪の毛)は、莎髻(ルビ:しゃけい)と称される小さな髷(まげ)のように結った髪型で七つに結ばれていることから「七莎髻(しちしゃけい)」ともいわれ、頭の上に開蓮(ルビ:かいれん、蓮の花が咲いている)。または莎髻(ルビ:しゃけい)と呼ばれる蓮花が咲いていない形状のものもある。毛を束ねて垂らす弁髪(ルビ:べんぱつ)も不動明王の髪型の特徴のひとつである。中にはパンチパーマのような縮れた短い毛をした彫像もあるが、そのようなヘアスタイルの違いがあってもお下げがついているのが定番の髪型だ。
顔は、左右につり上げられた眉、見開いた両目で性格の嶮しさを伺わせる。上唇で下唇を噛んでいるが、犬歯が見える。当初は両牙を下方に出していたが、その後は右牙を上に出し左牙を外側に出しているものが一般的となった。両牙がともに上向きなものもある。そのように顔面のデザインには詳細な違いがあるが、どれもが眼光厳しく憤怒の表情である。背光には燃えさかる炎が添えられている。文様としてあしらわれるのではなく炎そのものを具体的なモチーフとして背光に表すのが常であった。
そのような不動明王の様相について加藤周一はこう書いている。
不動明王が隻眼(ルビ:せきがん)(左目がつねに閉じられている)で童顔であるのは、彼がもともと超越した存在ではなく、人間より下の存在から上へとつきぬけたためだ。すなわち不動明王は、衆生の下から上に向かう運動を助けるのである。この上昇は、人から煩悩を取り除く―煩悩の無明(ルビ:むみょう)から解脱(ルビ:げだつ)の光明(ルビ:こうみょう)への―過程となる。不動明王は右手の剣と左手の羂索(ルビ:けんさく)で煩悩を断つのであり、右の犬歯で下唇を、左の犬歯で上唇を噛む憤怒(ルビ:ふんぬ)の相は、その苛烈な戦いを象徴している。この世のいかなる悪をも打ち負かす不動明王の力の激しさは、つねにその背後に燃えさかる火焔(ルビ:かえん)の破壊力によって象徴され、またそこには、火の持つ浄化作用も見ることができる。(※引用:加藤周一は『日本その心とかたち』P64)
人々を帰依させる苛烈な闘いを引き受けるこの武闘派の神は、光背の火焔が表す火の浄化作用と破壊力で人々を怖れさせるが同時に安堵感を与え魅了した。
・藤原時代の密教
唐は9世紀末頃から勢力が後退し始めて907年に滅亡した。中国と日本の公的な国交も途絶え貿易商人たちによる交流のみが行われるだけとなった。このような変化によって奈良時代から続いた大陸の影響は弱まり、平安時代中期以降から国風文化と呼ばれる日本独自の文化へと変わっていった。(※参照:『日本美術史』P54)
4世紀も続いた平安時代の中で最初の1世紀を弘仁・貞観時代というのに対して,寛平6 (894) 年に遣唐使を廃止した以後の平安中期と後期(「遣唐使廃止」の894(寛平六)年から「平家滅亡」の1185)は、藤原氏が摂政・関白の地位について実権を 振るった藤原時代と呼ばれる。宮廷文化に代わって、貴族による政治の支配が行われた。この時代には貴族による高度に洗練された優雅で繊細な文化が育(ルビ:はぐく)まれた。文学の世界では、仮名文字が普及した。美術では,寝殿造,やまと絵をはじめ,書,衣装などで、宗教では,天台,真言とならんで浄土教が発展し,神仏習合の思想が進められた。
藤原時代になっても、密教は以前貴族階級への強い影響力を持続していた。憤怒の不動明像は最も大衆的な仏像として王藤原時代にも広く信仰の対象とされていた。
「五大力菩薩像」(ルビ:ごだいりきぼさつ)(*図)(有志八幡講一八筒院)(ルビ:ゆうしはちまんこうじゅうはちつかいん)は護国祈願の仁王会(ルビ: にんのうえ)でもいられた3mを越える巨大な布に描かれた畏敬の尊神で、火焔を光背にした五大力菩薩像の憤怒像が威圧的な迫力をみせる。
大日如来の化身とされる憤怒する尊格の不動明王も、引き続き信仰の対象として流布していて、青蓮院(ルビ:しょうれんいん)の「不動明王二童子像」(通称、青不動)(*図)は、風格とともに、不動明王の尊格の存在感を深く思い知らされる図像である。
・千手観音
不動明王と時を同じくして、平安時代には観音(観音菩薩)の信仰が盛んになった。奈良時代後期(天平時代)に信仰をあつめた十一面観音像に代わって、多くの千手観音像が平安時代以降から造られるようになった。女神を祀った日本の土着的な信仰と共通項を思わせる千手観音像は、それぞれの手に人を救うための道具を持つ仏像で、その意匠は具体的な救済を視覚的に表すものであった。(※参照:加藤周一『日本その心とかたち』P63)
いまも日本の大衆的な崇拝の対象として信仰されている観音と不動明王は、平安の時代に大衆的な仏像として崇拝の対象なっていった。
仏教には罪(煩悩)と救いに対する二面的な性質をもつ。慈悲深い仏により罪があっても救われるとしながら、罪を克服すれば救われるという矛盾した教えを説く。慈悲深さの方は観音によって救われると説くのだが、同時に、不動明王によって贖罪が求められた。平安時代を通して、このような二面性を抱えた日本的仏教が広く普及していくのだが、その象徴として信仰をあつめたのが、不動明王と観音であった。
・不動明王と密教のまとめ
日本特有の仏教における信仰対象で、仏法僧の三宝を守護するとされる「三宝荒神」(ルビ:さんぽうこうじん)や、同義の「かまど神」、「庚申信仰」(ルビ:こうしんしんこう)の「本尊青面金剛」(ルビ:しょうめんこんごう)、「馬頭観音」(ルビ:ばとうかんのん)、日本神話の「猿田毘古神」(ルビ:サルタヒコノカミ)と「天狗」(ルビ:てんぐ)、そして「須佐之男命」(ルビ:スサノオノミコト)の神話などの偶像や図像にも、不動明王、あるいは密教に関連したような闘神や、神に等しい超人的な対象―怒濤の尊格に向けられた畏怖の念が混在した信仰が成立して、現在まで長く崇拝の対象とされてきた。
平安の時代になると、思想文化における中国からの影響が薄れ、文化や仏教思想はより日本的な独創性をもつようになっていった。平安時代には仏教の習合的変容も再び起きた。大乗仏教がとりわけ日本的な思考となり、趣向性を変えたのがこの時代であった。
すでに書いたとおり、日本古来のアニミズム的宗教は表象的イメージ(偶像)や教義、社を持つものではなかった。神の存在は元々不可視なもので、依り代によって知ることのできるものとされてきた。それが仏教の伝来と共にもたらされた神像の造形表現によって表象が行われるようになった。仏教伝来とは日本の美術表現、とりわけ仏や神といった人の形状イメージのベル・エポック的な事件であった。
それ以降の仏像、尊格イメージの歴史は、中国の影響を受けなくなるにつれて、日本独特の特徴なりをもつようになるわけだが、祈りを通して、その力が振るわれるという不動明王しかり、大衆的な嗜好で選択されるように信仰されてきた日本の仏像は少なからず怖さを主張するものが少なくない。
仏教はそれまで崇拝されていたあるいは日本的土壌の影響を受け、日本的な信仰として変容した。日本の土着的信仰の方も、新たな宗教や文化へと変わりながら存続したわけだが、それらの地場的な神々の偶像や図像を創造するよう仏教は機能し続けてきた。
仏教習合の歴史とは、まるで外的生物の侵入によって、ガラパゴス的土壌で、駆逐と淘汰、あるいは交配的融合が進んでいったのと等しく。優性的であって適性をもつものが残ったとか、その生存している環境に耐久性がある動物が残るといった生物的な適応性はいっさい当てはまらない。それよりも、人々に受け入れられたかどうか、すなわち、時代の流れの中で、支持されたかどうかの方が重要な要素であろう。むろん、みための図像だけではなく、思想的的確さといった様々な条件によって決まる問題であるのは当然なのだが、そうであったにしても、これほど怖い神々の御姿を日本人が祀り続けてきたのは事実であり、なにかしらの理由があると思われる。さらに前述した三宝荒神や、天狗や、須佐之男命など、不動明王のイメージが、様々に飛び火しつつ、多様な怖い尊格を成立させているというのも、なにかしらの魅力なり求心力がなくては説明がつかない。
なぜ、インドの影響を多分に受けた不動明王がこれほど永い時間、変わることなく愛され続けたのか… おそらく、その理由は、アジア、とりわけ日本的アニミズム、恐れの精神と怖さに憧れる思考が介在しているのではないだろうか。すなわち、日本というアジアのモンスーン的風土や、世界に対する姿勢が、深く関与しているのではないか。むろん、それは中国、インドを中心に据えた東南と東アジア地域全体にいえるのだが、アジア独特の感性、さらに極東の日本の風土や環境によって生成された美意識や、尊格に対する態度として捉えるべきであろう。
A-3 モンスーンの信仰―和辻哲郎「風土」論
倫理学者の和辻哲郎(一八八九~一九六〇年)は、著書『風土―人間学的考察』(一九三五年)で世界の風土を「モ ンスーン」「砂漠」「牧場」の三つに分けて、人類の文化を論じた。
自然の恩恵に溢れている「モンスーン」気候の、日本や東南アジアの人間にとって、自然は崇拝するか、絶対視する対象である。豊かさを与えるだけでなく、時に荒ぶるモンスーンの自然の中で生きる人間は、自立性が弱く、自然に対して畏敬の念を抱き、共存を願う思想を形成する。
比べて「砂漠」の人間は、過酷で敵対的な自然の中に置かれているため、逆らいようのない絶対的な力をもった自然と対立するが、支配的な存在としての「神」を想像するようになる。
神教的世界観はそのような砂漠的風土によって生みだされた。一方でヨーロッパの「牧場」の風土は、モンスーンのように恵みが豊かではないが、砂漠ほどは過酷ではない。そのため人間は、理性を働かせれば、自然は制御できるのだと考えるようになる。それゆえ牧場的な風土に住む人間は、理性と人間中心のヨーロッパ的思想を生みだしたと和辻は論じている。(※参照:佐々木成明『砂漠芸術論―環境と創造を巡る芸術人類学的論考』P13)
風土と環境は、我々人間の文化に大きな影響を及ぼすものであるが、人間の芸術的活動や、芸術嗜好、または宗教的思考性においても多くの影響を与える。日本は和辻が論じた「風土論」の三分類のひとつ「モンスーン」に位置するが、人間個人としての自立性を確立しにくい反面、地縁で結びついた村集団や、信仰を共にする共同体を成立する傾向が強く、自然に対して畏敬の念を抱き、自然崇拝―アニミズムの信仰を形成してきた。すなわち触らぬ神に祟りなしということわざが表すように、紳とは環境そのものであり、与えると同時に一瞬で奪い去る、わかり合える対象ではないという思いが信仰の根底にあって、恐れながら祀るといった姿勢で神との共存を願う宗教観を形成してきた。
むろん、そのようなモンスーン風土に根ざした文化を形成してきたのは日本だけでなく、中国やインドを含む広域のアジア・モンスーン気候の地域全域で、同様の宗教的指向性が指摘できる。ヒンドゥー教や、古代インド系の宗教、中国に根ざした道教しかりであろう。そうでありながら、日本の宗教や芸術における、他のアジア地域、大陸と異なる特性がある。
「孤立した文化に特徴的なのは、技術的な停滞ではなく、むしろ伝統的技術の洗練である」(*引用:加藤周一「日本その心と形」P24)と加藤周一は書いたが、同様に思想も洗練され極度にその特異性を際立たせていく。密教の不動明王や闘神の彫刻群、または見放すようでありながら聡明さや崇高さをアピールする観音像などが、その最たる例ではないだろうか。
またこのガラパゴス的芸術の土壌は、古来から京都圏の一極集中型の文化圏を中心で成立していて、大陸から届く情報や美術の輸入のルートも、延々と同じルートでもたらされてきたという得意な構造におかれてきた。そのことは、リファレンスとなる前史を参照しつつ、つねにこれを拡大していくか、根底に貯蔵されている文化への回帰を忠実に繰り返す。(これについては最終章で詳しく論考していくが)丸山眞男が「古層論」によって明らかにしようとした日本文化の構造とは、これら宗教、その尊格の表象と美意識にも同等に機能してきたのではないか。
本講が論じる怖さを模倣するようにして創造されてきた日本独特の畏敬と怒りの表象の萌芽のひとつが、この密教と不動明王を初めとする威嚇する尊格の歴史に辿ることができる。
密教がインドや中国で滅び、日本とチベットにのみ存続したという事態を踏まえて、日本が密教の奢れる神への信仰とその美意識を存続させ、得意な怖さを讃えた美意識をもったというのは性急すぎる。インド・ヒンドゥーは仏教を習合させるようにその信仰を現代に繋げてきた。ビシヌス神をはじめとするその特徴的な神々を表す表象や、勇敢な神々の闘いの物語を語り継ぐ神話も、日本の密教に散見できる表象と同一の怖さを伺わせる。そうでありながら、密教が信仰を集めた平安時代以降から、しだいに強力な影響力をもつようになっていった武士の台頭などが、互いに影響を及ぼしながら、日本独自の怖さを讃える美術や趣向が、この密教の信仰と尊格の表象を出発点として、形成されていったのではないか。
高野山金剛峯寺 根本大塔
東寺
天地眼の相で、宝剣・羂索を持ち、岩座上に立つ。不動明王は本来、醜く肥った童子の姿につくられるのであるが、本像は動きのない細身のからだで、着衣も身体からはあまり離れず、全身から静かに滲み出る怒りを表現しているようである。裳には華麗な彩色文様がほどこされ、衣文に添って截金(きりかね)の線が見られる。藤原時代の繊細な作風をよく伝える像である。
B 浄土教の普及と穢土の不安—鬼、地獄、死の恐怖*平安後期―乱世の時代の中で―末法の世の死生観 中世の不安が創造したペシミステック・アート
B-1 浄土教の世界観
・淨土と穢土の挾間で
浄土教はこの現世は情欲が溢れた穢土であり、浄土を求めないかぎり人は地獄に落ちると説き、極楽往生するには、一心に仏を想い念仏の行をあげる以外に方法はないとする。
このような世界観を説く浄土教は、知恩院(ルビ:ちおんいん)に残る「阿弥陀二十五菩薩来迎図(早来迎)」(ルビ:あみだにじゅうごぼさつらいごうず)(*図)(鎌倉時代 13-14世紀)など、数多くの二十五菩薩来迎図が鎌倉時代に描かせた。それらの仏画では臨場感が強く強調されていて、死に即したものを阿弥陀が瞬時に降臨して迎える様子が、現実感あふれる出来事として信者たちに訴求するよう描かれている。風にたなびいて尾がちぎれた雲と、その上にのる二十五人の阿弥陀仏一行は、まるでスポットライトを浴びるか、光り輝いているかのようで、廻りの景色が暗く見える。
同じく光り輝く巨大な阿弥陀が描かれているのが、「山越阿弥陀図」(ルビ:やまごえ)(*図)(金戒光明寺13世紀)で、山の峰の先から転法輪印(ルビ:てんぽうりんいん)を結んだ阿弥陀仏の来迎を表す。この山を越えて来迎する阿弥陀は平等院鳳凰堂扉絵(11世紀)にも見られる。(*参照:辻惟雄監修『日本美術の歴史』P192)
これらの図像はどれも阿弥陀が目の前に表れると行った超現実的な出来事が演劇的な趣でドラマチックに描かれている。
また弥勒菩薩が住まう浄土にある兜率院(ルビ:とそついん)の有様を描いた「兜率天曼荼羅図」(ルビ:とそつてんまんだらず)(岐阜誓願寺)(*図)なども、鎌倉時代に数多く描かれている。(※参照:辻惟雄監修『日本美術史』より宮崎新一「鎌倉時代」P93)
浄土教の普及は良源(912~985年)と弟子の源信(942~1017年)による功績が大きいとされる。良源は『極楽浄土九品往生義』(ルビ:ごくらくじょうどくほんおうじょうぎ)を著して、念仏とその他の修行の重要性を説いた。一方の源信は寛和元年(985年)に極楽往生に関する重要な文章を集めた仏教書『往生要集』(ルビ:おうじょうようしゅう)を著し、 極楽浄土と地獄の様子を詳細に表した。この書物で説かれた地獄・極楽の観念、厭離穢土・欣求浄土の概念は、貴族だけでなく庶民にも広く普及し、後の宗教と思想、日本人の倫理感にも大きな影響を与えたといっていいだろう。(※参照:山本聡美『闇の日本美術』p26)
『往生要集』は全十章で構成された書物で、第一章は厭離穢土(ルビ:えんりえど)では、地獄・餓鬼・畜生・阿修羅・ 人間・天人で構成される六道を説くもので、現世で人間であっても、罪を犯せば因果応報(ルビ:いんがおうほう)によってこの六道の世界に永久に輪廻転生(ルビ:いんがおうほう)し続けると説いている。
この世界(閻浮提(ルビ:えんぶだい))の地下には、層をなして広がる八つの地獄があるとして、その怖さを解説する内容で、読む者に強い衝撃を与えた。体系的に紹介されるこれらの地獄と、その怖ろしい責めは、現世での罪の重さしだいで、より深いところに落とされていくと説明されていた。(※参照:山本聡美『闇の日本美術』p26)
浄土教を支持した貴族階級の中心的存在は藤原道長と頼道の父子であった。父道長は阿弥陀像を本尊とする阿弥陀堂「無量寿院」を建造して、京都に法成寺(ルビ:ほうじょうじ)を建造した。頼道は「平等院鳳凰堂」(1053年)(*図)を建てた。現存する平等院から伺い知るとおり、阿弥陀の尊格と浄土世界が輝かしい世界として作り出されていた。
B-2恐れの美術
・穢土を生きる人々の感性
絢爛豪華な貴族社会の様をよそに、繰り返された権力闘争を原因として、京都の治安は悪化して、武器の携帯が必用なほどの状態になっていた。応天門の変を題材にした平安時代末期の絵巻物「伴大納言絵巻」(ルビ:(ばんだいなごんえことば)(*図)に描かれているような大火や、飢饉が繰りかえし起きた。盗みや殺人が横行する世の中は、まさしく源信が表した情欲が溢れた穢土を彷彿する世界であっていた。そのような現世と繋がっている地獄に落ちる恐怖と不安が、極楽浄土へいけることへの切望を強固なものにして、阿弥陀来迎が切望された。(※参照:加藤周一『日本その心とかたち』P81)
一方で、12世紀末期には『地獄草子絵巻』(ルビ:じごくそうしえまき)、『病草子絵巻』(*図)(ルビ:やまいそうしえまき)、餓鬼草子絵巻(ルビ:がきそうしえまき)など、人々の不安が表層化されるような絵巻が残る。現世の不安からだれもが地獄へ興味をもっていて、怖いもの見たさの欲望が、地獄草子絵巻を望んだのか。
この時代に人々の不安感の高まりをもっとも顕著に示すのは「末法思想」―すなわち終末論の広がりだ。「釈迦が説いた正しい教えが世で行われ修行して悟る人がいる時代(正法)が過ぎると、次に教えが行われても外見だけが修行者に似るだけで悟りにいたる人がいない時代(像法)が訪れてしまい、その次には人も世も最悪となり正法がまったく行われない時代(=末法)が来る」(※引用:ウイキペディア)とする終末論的歴史観である。特に1052年(永承7年)が末法元年として恐れられ、経典を土中に埋納する経塚造営が盛んとなった。平安時代も終わりが近づき、貴族の摂関政治が衰え始め院政へと移行する時代におきた未来予兆である。武士の台頭が始まり、仏教界では諸寺間の争いや腐敗がおきていて、僧兵が出現するなど、混乱が続き、治安も悪化していた。民衆たちは現世と死後世界の不安から、末法の予言を社会情勢と重ねて捉え、より厭世的な思想をもつようになっていて、そのような世相が極楽浄土(ユートピア)への憧れをより強くしていた。
浄土教における阿弥陀如来による救済は、前述した阿弥陀如来迎などで表されたが、反対にあった現世への不安と刹那思考から描かれたのが「六道絵」(註釈)(*図)や、死後の不安を表象する「地獄草子」(*図)、屍となって消えていく人の儚さと残酷さを描いた「九相図」(*図)または「餓鬼草子」(*図)、「病草子」(*図)といったペシミステックな芸術作品であった。
・六道絵
平安時代と変わらず乱世を生きる宿命におかれた人々の不安や恐怖感は、鎌倉時代になっても仏教説話図に強く反映されていた。聖衆来迎寺(ルビ:しゅうじゅうらいこうでら)に残る巨大な「六道絵」(*図)は「往生要集」の所説を絵にしたもので、一作が一五五・五センチメートル×六八・〇センチメートルの掛け軸が一五幅セットになっているという巨大な仏教説話図の絵画である。(※参照:山本聡美『闇の日本美術』P031)
葬られた美女の身体が腐敗して野犬に喰われ、骨と化す惨状が、生々しい色彩と写実的な技法でリアルに描かれている。九相図や、六道が一二幅、念仏功徳の説話が二幅、地獄の閻魔王庁が一幅の計一五幅で、「往生要集」が解き明かす世界を壮大な世界観で描く。(※参照:辻惟雄監修『日本美術の歴史』P190)
このような仏教説話図は絵巻だけでなく障屏画や掛け軸でも展開されたが、大陸からもたらされたリアルな描写の宋仏画の影響もあって、鎌倉時代には現実感と臨場感が強調された作品が数多く作られた。
・餓鬼 - 地獄の哀れVS釈迦
餓鬼の世界は、六道の中でも特に苦しい世界として、地獄・畜生の世界と併せて三悪道とされる。平安時代末期に描かれた「地獄草子」と(*図)同じころから「餓鬼草子」(*図)が制作された。
餓鬼草子の餓鬼は頚が細く、手足はやせこけているが、腹が肥大していて、浅黒い体をしている。常に餓えに苦しむ姿で表 されている。死体や糞尿を食らい、すさまじい責め苦を受けるとされていて、残されている餓鬼草子は、そのおぞましくも切なく哀れな様が表されている。
「餓鬼草紙」[京都国立博物館本](*図)は、平安時代後期(12世紀)に描かれたもので、段ごとに出典が異なる餓鬼救済の物語が集められている。
第1、2段には、三十六餓鬼のうちのひとつで、お酒を水で薄めて売ったり、蛾やミミズを混ぜるなどといった酒に関する悪行を行った人間が転生するという食水餓鬼の受苦の様子が描かれている。食水餓鬼は水を得ることが出来ない苦難に苛まれていて、第1では墓に手向けられた水のしたたりをなめて、わずかに命を保っている。続く第 2段では、卒塔婆に水を掛ける人びとを描かれていて、そのような餓鬼道に堕ちた者であっても、残された人びとの供養によって救われることが説かれている。
第3、4段では、釈迦の弟子のひとり目連が釈迦に救済の方法を教えられて、餓鬼道に堕ちた母を救う説話が描かれている。
第5段は、仏の慈悲で、水を飲めずに苦しんでいた餓鬼が、水が飲めるようになり、仏国土へ生まれ変われたことを描いている。
第6段は、体はやせて細く、のどは針のようで、いつも口から火を吐いている焔 口餓鬼(えんぐがき)の苦しみを聞いた釈尊十大弟子の一人阿難が釈迦から救済のための呪文を教わったことが描かれている。
そして第7段では、阿難から餓鬼救済の方法を教えられた僧によって飲食物を供えて経を読む施餓鬼(ルビ:せがき)の供養が施されたことを表している。
「餓鬼草紙」(絵十図・河本本)(*図)[東京国立博物館]は平安時代末期~鎌倉時代の絵巻物で、墓地で死肉と骨を喰らう餓鬼の群れや、貴人の暮らしの中に紛れ込んだ餓鬼、鬼によって責められている餓鬼の様子などが10編のシーンとして描 かれている。
その一段には平安京域内(洛中)の小路で排便する人間達(庶民)と、人間の糞便を食いたくてたむろしている食糞餓鬼(ルビ:じきふんがき)が描かれている。(※参照:山本聡美『闇の日本美術』P29,P42)(*参照:山本聡美『闇の日本美術』P29,P42)(文化遺産オンライン 紙本著色餓鬼草紙、紙本著色餓鬼草紙)
B-3 鬼 見えざる力 武家―もののふの鬼退治ともののけ、妖怪 ~浄土、仏、地獄(九相)思想に支えられて登場した妖怪と鬼、もののけ
・鬼に集約する怖さのイマジネーション
中国語の鬼は日本の霊と同義の言葉であり、鬼籍というように、元々は霊魂のような存在を我々は鬼と称していた。
それとは異なる捉え方が日本で定着したのは中世であった。
当初から「おに」とよばれる存在ではなかったようだ。馬場あき子『鬼の研究』によれば、「おに」の語は「おぬ(隠))」が転じたもので、元来は、中国で鬼が霊を指す詞であるのと同じく姿の見えないもの、この世のものではないものを意味する。そこから人の力を超えたもの、そこから災いをもたらすモンスター的な存在のイメージに発展したという。さらに平安・鎌倉時代に陰陽思想や浄土思想的な見解が加わり、地獄の獄卒として表されたのだろうか。あらためて指摘するなら、前述の「往生要集」に標された六道にのひとつが餓鬼道であり、そこに転生した哀れな餓鬼にも鬼の字が使われている。(※参照:馬場あき子『鬼の研究』)
奈良時代の文献によれば、古くは、「おに」と読む以前に「もの」と読んでいて、「もの」とは怨恨を持った怨霊で、邪悪な存在、祟る霊を表す言葉であったが、平安時代末期に「おに」の読みにとって代わられたとされる。
鬼は口頭神話で表される存在だけでなく、平安から鎌倉に至る時代に、鬼は絵画や物語として広く知られていて、さらに怖いもの、不吉なもの、畏怖の対象として知られていた。
鬼とは一般的に邪悪なものとして捉えられるが、仏教、またはヒンドゥの神々や天部の中にも、風神・雷神、竜王や明王など、畏敬の姿で表される鬼神的な神格なども含んで考えるなら、超人的な能力や身体特性をもつ存在を、我々の祖先は鬼と表した。怒る神、触らぬ神に祟りなしというよに、両義的な神々の悪しき姿、あるいは裏側の姿が鬼なのかもしれない。
『大江山絵巻』(逸翁美術館所蔵)(*図)で描かれている鬼の酒呑童子がそうであるように、鬼は「童子」と名付けられる場合がある。これは子供ではなく、成人したあとも、元服後の髪型にならないで、子供のようなざんぎり頭のままであるためだという。人里離れた場所に「かつて鬼が棲んでいた」という伝説が残されている、あるいは表されるように、鬼は人がいない場所に住まう異形異様なもの、「邪しき神」として、古くから怖れられてきた。一方で「鬼武者」という表現がそうであるように、孤高のもの、達人を指すのも鬼である。
頭髪がちぢれていて、二本か一本の角が生えている。口に牙があり、鋭い爪をもつ。色は赤・青・黒などで、虎の皮のふんどしや腰布をつけていて、金棒を持った大男というのが典型的な鬼の様相として、永く伝えられている。地獄で亡者を責める獄卒としてのイメージも定着している。いずれにせよ、人智を越えた、目に見えない力のような存在を我々は鬼と称してきた。
・土蜘蛛草子と酒呑童子
「大江山絵詞」(ルビ:えことば)は、大江山に住む酒呑童子(ルビ:しゅてんどうじ)という名の鬼を源頼光(ルビ:みなもとのよりみつ)(948~1021)が退治する話で、頼光が知恵と武力で敵を討ち取るという、優れた武士のありようが描かれている。
実在した頼光の方はというと、都の中流貴族的な人物で、財力で摂関家と繋がりをもっていたような経歴が伝えられている。そんな人物がこのような奇伝英雄伝として後の世で描かれたのは、その父親源の満仲(ルビ:みなもとのみつなか) (912~97)の嫡男(ルビ:ちゃくなん)―長男であったためだと推測される。そして同じ清和源氏の家系である武家政権を打ち立て、鎌倉幕府の初代征夷大将軍となった源頼朝(ルビ:みなもとのよりとも)と同じく室町幕府の初代征夷大将軍となった足利尊氏(あしかが たかうじ)の武威と高貴な血筋を表すためであっただろう。
これの他に頼光を主人公とした武勇伝としては「土蜘蛛草子」(ルビ:つちぐもそうし)(*図)がある。こちらは頼光 が家来渡辺綱(ルビ:わたなべのつな)(954~1025)と共に京都郊外のあばら家で、次々と妖怪を退治する鎌倉時代に書かれた冒険物語である。
もっとも土蜘蛛の話はずっと古くから伝えられていて、『古事記』や『日本書紀』にも出てくる。古代日本の時代に、朝 廷に従わない異民族たちの異形の身体と原始的習慣を表し、怖れと軽視を含む呼称として土蜘蛛の名が使われていた。地を這い穴蔵の闇の中に住まう土蜘蛛のイメージは、不気味な妖怪としてこれまで神話・伝承、説話に表れる怪物として脈々と受け継がれていて、土蜘蛛が武士の武勇伝と結びつけられたのは容易に想像できる。(※参照:山本聡美『闇の日本美術』P65)
・桃太郎 あるいは丸と名付けられる子供、わらじ(子供)は聖なる存在。
だれもが知るおとぎばなしの桃太郎の物語も鬼退治の物語だ。家来を連れて鬼ヶ島まで鬼を退治しに行く若サムライの初陣物語と言っていい。口承話としての原型は室町時代末期から江戸時代初期頃とされる。(※参照:加原奈穂子 「昔話の主人公から国家の象徴へ―「桃太郎」パラダイムの形成―」 『東京藝術大学音楽学部紀要』 36巻 東京藝術大学音楽学部、51–72頁、2010年。 NAID120005607395)ただし、その時代の桃太郎は武家的装束を身につけた人物でなく、他の動物たちも家来的な役割よりも仲間のような存在として登場するものであったとする説も散見される。
中世の酒呑童子退治の武勇伝だけでなく、桃太郎の鬼退治は昭和の時代の大東亜戦争では、軍国主義化の国威高揚、敵国憎悪のためのプロパガンダに利用されていた。「鬼畜米英」という鬼を成敗する子として、桃太郎は、親孝行・正義・仁如・尚武・明朗を体現する国民的英雄として利用された。(※参照:野村純一他編 『昔話・伝説小事典』 みずうみ書房、1987年、254-255頁)
さて、鬼退治の物語でサムライの武勇伝が成立するためには、敵であって、成敗されて当然とされる鬼の存在がなくてはならない。前述したとおり、鬼とは、古くから特別な力をもつものを実在の存在として表したイメージで、怖さとともに、にくさ、その裏腹に、孤高の存在や、力あるもののたとえでもあった。
怖いものが与えてくれるトラウマ的なイマジネーションは、その反対に、怖いものへの同化や模倣も成立させる…
・キールティムカ―ヒンドゥの聖獣
屋根瓦に添えられる「鬼瓦」がそうであるように、鬼は、シャチホコや、狛犬と同じく、魔除けとして用いられてきた。鬼瓦は唐の文化を積極的に取り入れた奈良時代から急速に全国に普及したという。
ヨーロッパの建物に見られるガーゴイルや、古くはローマ帝政時代のパルミラ(現在のシリア)で髪の毛が蛇の怪物メドゥーサが厄除けとして設置してあったり、あるいは魔除けの聖獣キールティムカ(Kirtimukha)と呼ばれる獅子とも鬼とも思われる像も、同じように悪しきものから守護してくれる鬼面として、インド以東の広範囲の南アジアとの国々で散見される。
ヒンドゥー教寺院建築と仏教建築の図像であり、巨大な牙と、口を開けたどう猛な顔だけの聖獣である。インドネシアなど東南アジアではしばしばカラと呼ばれ、 中国では「 貪欲 」という意味のタオティーとして知られている。
キールティムカは大きな目、まるい団子鼻で、大きく開いた口から歯がむき出していて、その多くは顎がない。顔だけの鬼、キルムーティカとは、インド神話に登場する食欲旺盛な怪物で、自らの手、足、体を食い尽くして、顔面だけになってしまうのだが、シバ神が、その激しい性格を讃えて、「ほまれ高い顔」を意味するキールティムカと名付けたと伝わる。
そのような逸話が残るキールティムカも鬼と同じく、怖しい存在、畏怖の対象、魔除けの力をもつ聖獣でありながら、威厳や、栄誉を表す象徴で、中国や日本で鬼として捉えられているものと等しい。繰り返しになるが、憤怒の表情で知られる不動明王や、鬼瓦も、キールティムカと繋があるし、祇園祭における「牛頭天王」の信仰や、「馬頭観音」や、「観音菩薩」とも深く関連性をもつとされる。(*参照:立川武蔵『聖なる幻獣』P52)
・鬼、怖れの美術 まとめ
前章で触れたとおり、密教の尊格を通して、いかつさをもって、邪悪なる者をけちらす、日本的な怖さを讃えるイメージが成立していった。闘神信仰によって培われた美意識や美術である。
畏怖の念がどのように,その後の日本的美術や、畏敬のイメージを成立させたかについての論考は後述となるが、その資源的な密教仏、闘神の表象と比べて、本章が扱った浄土教の仏尊は優しさと慈愛にみちている。これらの仏像が誘う浄土というユートピアへの憧れと背中合わせに、穢土的な現世や、地獄や、暴力や、死についての人々の怖れ―ペシミステックな想像力が生み出したイメージの数々が、この時代に数多く描かれた。
鬼への怖れをその一つとして挙げられる。
一方で鬼などの悪しきもの―ビランを退治する武家というヒーロー物語が成立したのもこの時代の特色のひとつといっていい。
悪しきもの、しかし力強い、絶対的な、浄土とは異なる、メタ現世といっていいような世界観を、一身にひきうけたのが鬼であった。
秋田男鹿半島で行われる年中行事「なまはげ」に登場するなまはげは、その異様な出で立ちで、広く知られる。神の使い(来訪神)のなまはげは本来鬼ではない。しかし、近代化の過程で鬼文化の一角に組み込まれ、変容してしまったという説が説かれる。(*参照:小松和彦『妖怪文化入門』2012年、150-152頁)
その発祥は不明で、もっとも古く文献に記されているのは、文政5年(1822年)に菅江真澄が記した『菅江真澄遊覧記』で、「牡鹿乃寒かぜ」において、文化8年1月15日(1811年2月8日)に秋田の小正月行事「ナモミハギ」が行われたと記されている。(*参照:秋田県立図書館蔵書『菅江真澄遊覧記』)また、秋田には「漢(前漢:紀元前206年 - 8年と後漢:25年 - 220年)の武帝が男鹿を訪れて、5匹の鬼を毎日のように使役していたが、正月15日だけは鬼が解き放たれて里を荒らし回った」という伝説があって、これをなまはげの起源とする説もある。(*参照:野添憲治・野口達二『秋田の伝説』「日本の伝説」23-24頁)
鬼、来訪神、マレビト、妖怪、様々な伝承が日本中に残され、いまだに信仰をつないでいるが、その中には、なまはげに代表されるような畏敬の形状の人ならぬ者が多い。
日本各地の山間地帯には「かつて鬼が棲んでいた」という伝説で残されている。中世を通して成立していった「能」では、嫉妬心から鬼と化した女性の逸話が描かれ、「般若の面」そしてその様態を表そうとする。
馬場あき子は日本の鬼の伝承を5種類に分類している。1.民俗学上の鬼で祖霊や地霊。2.天狗など、山岳宗教系の鬼、山伏系の鬼。3.仏教系の鬼、邪鬼、夜叉、羅刹。4.人鬼系の鬼、盗賊や凶悪な無用者。5.怨恨や憤怒によって鬼に変身の変身譚系の鬼。前述の「~~童子」などは4の人鬼系の鬼、盗賊や凶悪な無用者に分類されるだろう。密教の尊各たちが踏みつけている邪鬼などは3の仏教系の鬼であろう。地獄の獄卒の鬼にいたぶられる餓鬼もまた鬼の文字をかざす。
鬼とは人ならざる人である。ホラー小説の作家平山夢明(ルビ:ひらやまゆめあき)は、「人間は〈人間の形をした人間でないモノ〉を怖れる反面、〈人の形をしていない怪物〉は、そこまで怖がらない」と書いていた。フランケンシュタインやゾンビやピエロやエイリアンに比べて、植物や煙など不定形の化け物はそれほど怖くないのだという。鬼とは確実に前者〈人間の形をした人間でないモノ〉である。平山はその理由として、「人間に似た怪物というのは、つまるところ変容した人間〈完全な不完全〉だかれではないか」「自分たちとそっくりでありながら、自分たちとは異なる存在」であると論じる。(*参照:平山夢明『恐怖の構造』P26「」括弧内は原文から*引用)
鬼も同様で、「自分たちとそっくりでありながら、自分たちとは異なる〈人間の形をした人間でないモノ〉だろう。
中世の時代に表れた鬼への恐れは、その後様々な形で鬼への信仰や、強靱なもの、孤高の存在を鬼と喩える独自の文化を成立させてきた。武芸の達人を「鬼武者」と呼び、強い酒を「鬼ごろし」と喩え、 人間とは思われないほど優れた才能を「鬼才」(ルビ:きさい)と称する。
鬼は忌み嫌われる怖くて、非常なだけのものでなく、どこか俗世を離れて生きていく、人間離れした意思や肉体をもつ人物への賛美でもあったのだ。そのような日本的な意識がいつ頃から成立したかは不明であるが、ここに挙げた通り中世の時代に、山岳信仰などそれまでの原始的宗教と、仏教が習合化され、さらに戦乱・災害・飢饉などの社会不安の中で頻出する人死にや行方不明といった惨事を説明するために、あるいはその原因を擬人化するために鬼は必要不可欠な対象であった。
鬼とは中世の人々の恐怖を具現化したものであって、現在に至るまで怖い物の代名詞として怖れられている。(*参照:吉成勇編 『日本「神話・伝説」総覧』 新人物往来社〈歴史読本特別増刊・事典シリーズ〉244-245頁)
「兜率天曼荼羅図」(岐阜誓願寺)
酒呑童子
『大江山絵詞』(大江山絵巻)によるあらすじは次のとおりである。
一条天皇の時代、京の若者や姫君が次々と神隠しに遭った。安倍晴明に占わせたところ、大江山に住む鬼(酒呑童子)の仕業とわかった。そこで帝は長徳元年(995年)に源頼光と藤原保昌らを征伐に向わせた。頼光らは山伏を装い鬼の居城を訪ね、一夜の宿をとらせてほしいと頼む。酒呑童子らは京の都から源頼光らが自分を成敗しにくるとの情報を得ていたので警戒し様々な詰問をする。なんとか疑いを晴らし酒を酌み交わして話を聞いたところ、大の酒好きなために家来から「酒呑童子」と呼ばれていることや、平野山(比良山[4])に住んでいたが伝教大師(最澄)が延暦寺を建てて以来、そこには居られなくなり、嘉祥2年(849年)から大江山に住みついたことなど身の上話を語った。頼光らは鬼に八幡大菩薩から与えられた「神変奇特酒」(神便鬼毒酒)という毒酒を振る舞い、笈に背負っていた武具で身を固め酒呑童子の寝所を襲い、身体を押さえつけて首をはねた。生首はなお頼光の兜を噛みつきにかかったが、仲間の兜も重ねかぶって難を逃れた。一行は、首級を持ち帰り京に凱旋。首級は帝らが検分したのちに宇治の平等院の宝蔵に納められた。
なまはげ
C 風流
C-1 キッチュ、作り物の美意識
・庶民による俗美術の登場
風流(ふりゅう)とは、中世に高揚した民衆の美意識である。 風流は平安時代から江戸時代に至る、おおよそ900年も続いた庶民による祝祭の文化運動だった。
現在の時代に風流と言えば、月を見たり、桜をめでるといった、どちらかといえば、自然を愛好して、その風情を楽しむ行為や、そのような行いで受ける感慨を指す美意識として使われているが、中世ではかなり異なる概念であった。それこそ数奇ないでたちや意匠、奇抜で人を驚かすような振る舞いを指す概念で、それこそ本稿が論考する「民衆の日本美術史」を表すような言葉であったといっても過言ではない。
この章では、本書籍のテーマである現代のヤンキーやギャルに通底する畏敬の美意識が、時代を超えて、創造を繰り返していくための、必修条件であった、世界的に類を見ない、日本の民俗文化の、特殊な美意識の相対である風流について論考する。風流とは、日本の民俗的美意識そのものであり、その独特の美意識を受け継ぎ、熟成させるための受け皿のようなものであった。
・風流の発生と熟成
中国語の「風流」とは、徳が人を感化することを風にたとた「徳風〈ルビ:とくふう)」が、のちの世に伝わっていくようなことを顕す言葉で、おもに政治教育の教えや論理、さらに倫理感や美的価値が、広く国民に普及していくといった理想的状況を表していた。これが、やがて詩仙道(※註釈)の理想とされるようになっていく。女性と交情をもちつつ、音楽・詩作、さらに酒宴で知的な社交談義が楽しめるような才覚をもつのが仙人の様であり、そのような生活を模倣することを「風流」と称するようになった。(※参照:尼ヶ崎淋『いきと風流―日本人の生き方と生活の美学』P43)
これがのちに日本に伝わって使われるようになったが、奈良時代末期に編纂されたと考えられる『万葉集』では、同様に、知識や、詩作と音楽的教養があって、なお酒の席でのムードを盛り上げられるような、クールでクレバーな人物という、中国からつたわった元の意味と結びつきを伺わせる言葉として使われた。さらにそのころの日本では風流は、もうひとつ「みやび」と読む言葉として使われたいた。
平安時代になると、「文雅」というような意味のものとして使われたり、清らかな自然風景を形容表する言葉として使われるようにもなっていった。自然の中にいる喜びを表すような、現代の我々が使う風流と同じようなニュアンスも多少含まれるようになっていたようだ。
カナで書かれた日本文では「みやび」と書くか、「風流」の語が日本語になって、「ふりぅ」と綴られていた。意味も異なっていて、ふりぅとは、見た目が派手な装飾や、そのような嗜好を表す言葉として使われていた。のちに、これが転じて、前述したような鎌倉時代の「風流」、すなわち豪奢なもの、祭礼で使う華やかな傘や鉾(ルビ:ほこ)など、デコレーション要素が強い装飾の物品を風流と呼ぶようになった。(※参照:尼ヶ崎淋『いきと風流―日本人の生き方と生活の美学』P72)
風流は固有のものを指すだけでなく、形容詞であり、金や銀を使い、得意な作りを施した豪奢な工夫や、美麗な様子を意味する言葉として使われていた。さらに「風流者」(ルビ:ふうぎもの)という言い回しもされていた。(※註釈=備考:『大鏡』)
その後「ふりぅ(風流)」は、特別な紛争で練り歩いたり、踊る様子や、そのような集団や、祭りの様相を表す言葉として使われた。豪華なもの、色とりどりなもの、驚愕するべきもの、または異様さもの、ストレンジな扮装や、装飾を指す言葉として使われるようになり、中世を経て、江戸に至るまで、永く同様の意味で使われていた。
風流という言葉で括られるようなカーニバルや、ページェント的なもの、または非日常的なものは、祇園祭りや、盆踊りといった、庶民を中心とする文化として今日まで脈々と受け継がれている。もともと風流には「みやび」とふりがなを振る言葉であったと書いたが、現代の我々が古い日本の宮廷・貴族文化を表す言葉として使う今日の「みやび」とは真逆の、庶民的な派手さなどを表す、対極の言葉として使われていたのだ。そして「風流」は、「わび」や「さび」といった、美意識とも対極にある美意識であった。
中世の風流は、趣向を凝らした「つくりもの」であったり、芸能のありようであったりと多面的で、明確に定義を定めるのは難しい。しかし、それは確実に庶民の側で成立した文化であって、支配者階級によって牽引されるだけではなかった。
それゆえ俗側の文化運動そのものを表す言葉であったと言えなくもない。広く捉えるならば、「風流」とは「中世における民衆芸術」そのものすべてを表す総合的な概念であった。
風流は民衆による芸能や美術・建築など、広範囲に用いられた言葉で、さらに、庶民の生活や宗教的行事の骨幹によこたわっていた。その嗜好は「俗の側の芸術運動」と類型するべきもので、風流は室町以降に表れる「数奇者」や「ばさら」さらに「かぶきもの」といった、庶民だけでなく貴族や武士までを取り込んで成立した風習や芸術的行為の骨幹に通底する、もっとも日本的な芸術の総体的概念であった。
すなわち、本書が論考を試みる「オラオラ的なる芸術志向、畏怖と豪奢の美学」におけるもっとも重要な概念である。
C-2 芸能としての風流
・すべての芸能の根源としての風流
日本の伝統的芸能と、宗教儀礼として奉納される神事の多くは、中世時代の風流に由縁をもつ、あるいは影響を受けているものが多いといってよいだろう。
「巫女神楽」、「湯立神楽」、「獅子神楽」などの神楽神事(ルビ:かぐらしんじ)や、「猿楽」(ルビ:さるがく)と習合しながら「能楽」(ルビ:のうがく)の源流となった「田楽」(ルビ:でんがく)や、三河万歳(ルビ:みかわまんざい)などの語り物や祝福芸能、祭礼行列(お練り)、さらに、念仏を唱えながら踊る伝統芸能「念仏踊り」や、。僧侶が寺の祭礼行事で演じる「延年」(ルビ:えんねん)など、芸能的要素が見受けられる祭礼行事も、風流から派生し、現在に受け継がれている祭礼芸能である。
そのような「風流」の趣向は、猿楽・能・狂言など他の芸能に大きな影響を与えた。そして、江戸期に成立する歌舞伎の萌芽にも深く関連性をもつものであった。
・風流踊り
中世の民衆たちに風流の精神と趣向を誕生させたのは数々の民間芸能であった。田楽(ルビ:でんがく)は、田植えの前に豊作を祈る田遊びや、耕田の儀礼で行われていた伴奏と舞踊に、仏教や鼓吹と結びついて格式化された芸能で、華美で異形な被り物などを着けて色とりどりの恰好で踊る民衆の芸能で、風流の精神と嗜好を決定的なものにした存在だった。田楽はいつしかカーニバル的な勢いを持つ催事へと発展していった。
室町時代を通じて、守護大名の権限強化と惣村・郷村の自立が進み、荘園は次第に解体されていった。荘園・公領に在住していた民衆によって、惣村(ルビ:そうそん)と呼ばれる村落が形成された。
南北朝時代以後になると、より民衆の団結・自立がより進んで、皇族・貴族、武士ではない、第三の群衆と呼べるような民衆の勢力が生まれた。
聖なるものたちと対峙する俗の集団、すなわち大衆という新しい文化共同体が形成されたといってもいいだろう。この新しい日本文化の担い手たちである都市の町衆と、地方村落の農村たちは、独自の祭礼や芸能の中で「風流」を取り入れ、育んでいった。
この頃から造作物だけでなく、派手な衣装に身を包んで笛や太鼓の音に囃されて練り歩く「囃子物」や、これに合わせて拍子を取る「拍子物」など、集団で踊りを演じる「風流踊」が出現した。風流踊は室町時代の後期から江戸時代初期にかけて大流行した。
ところで、風流という芸能は、嗜好を懲らした作り物を掲げ(ルビ:かか)、仮装して囃し(ルビ:はや)し踊るものであった。ことに囃しが特徴的だったので拍子物と呼ばれることもある。これが、盂蘭盆会(るび:うらぼんえ)における死者追善の念仏と結びついたのが、いうところの念仏風流・念仏拍子物(囃子物)なのである。奈良や京都の都市市民の間でことのほかにもてはやされ、その流行は、当時、全国を席巻する勢いがあった。(※引用:守屋穀『日本中世への視座 風流・ばさら・かぶき』P146)
「風流踊り」は、鉦・太鼓・笛など囃しものの器楽演奏や小歌に合わせて様々な衣装を着た人びとが群舞する踊りである。『豊国祭図屏風』に描かれている慶長9年(1604年)の豊臣秀吉七回忌における豊国神社の風流踊がよく知られているが、室町時代後期から江戸時代初期にかけて大流行して、風流と言えば風流踊を指すほどであった。江戸時代になると、一回性の趣向を凝らすといった奇抜さがなくなり、固定化された踊りとして各地の農村に定着していった。現代に受け継がれている盆踊り、花笠踊、祇園祭、やすらい花(葵祭)など、多くの民俗芸能、民俗行事、祝祭催事の源流が、この時期の風流踊りの影響を受けているといわれる。(※参照:尼ケ崎淋『いきと風流―日本人の生き方と生活の美学』P146)
「拍子物」と呼ばれた笛や太鼓の伴奏と流行の歌謡がつきものであった。この時代では「おどり」は「踊」の字ではなく、 「跳」や「躍」の字が当てられていたという。それは現在の「舞う」ような踊りではなく、「跳躍」するようなものであったと推察される。(※参照:尼ケ崎淋『いきと風流―日本人の生き方と生活の美学』P171)
風流踊りには「ひとつもの」と呼ばれた仮装(コスプレ)の集団がつきもので、町衆はみな知恵をしぼって、どのようにして華美でありながら人を驚かせられるかを競い合ったという。(※参照:尼ケ崎淋『いきと風流―日本人の生き方と生活の美学』P174-A)
・盆踊りへ
とくに盆の風流(踊り)は「念仏拍子物」と呼ばれ、祖先の霊を念仏で供養していた農村的な信仰と深く結びついていて、壮大な規模で執り行われていた。この時代の盆とは、旧盆(七月の一五日)の満月の日で、晴れていれば一晩中明るい。
京都の町で盆の風流踊りが流行するのは、応仁の乱、文明の大乱を過ぎた戦国時代初期であった。(戦国の世とはいえ、年中ずっと戦が続くわけではなかった。)(※参照:尼ケ崎淋『いきと風流―日本人の生き方と生活の美学』P171) 武士や公家の政治や事業にも愛想を尽かし、鬱積していた庶民のエネルギーがこのような祭で爆発していたのだろうか、そのような風流踊の流行は、民衆(京都の町衆)の豊かな経済力に支えられていた。そして派手な踊り子たちの衣装は、この時代に京都で作られていた工芸や染織の技術によるものであった。
京都の人にとって「先の大戦」とは第二次世界大戦でなく応仁の乱だという笑い話があるが、天下を狙う戦国大名たちが上洛を目指したこの時代で、もっとも戦禍を免れたのが京都であった。京都の洛中洛外ではそんな戦国大名による宮廷の修復や寺院の再建などが終わりなく続いていた。それゆえ土木・建築事業で民衆も潤っていて、京都の町は戦国時代であろうと活気に溢れていたと思われる。(※参照:尼ケ崎淋『いきと風流―日本人の生き方と生活の美学』P176)
そのような土木事業の完成を祝賀や、春の花見、秋の紅葉狩りなど貴族的な行楽が庶民のものとなり、「花下群舞図」などに描かれているような風流の宴と跳躍の踊が年中開催されていて、その人出を目当てに茶やが店を開くという、現在の日本と変わらない風景が、この戦国の時代に成立していた。(※参照:尼ケ崎淋『いきと風流―日本人の生き方と生活の美学』P174)
すがたかたちがどうであれ、政治権力はこうした民衆の風潮を集団的濫行(ルビ:らんぎょう)と捉えて警戒して、過度な風流を禁じる命令を繰り返し出したが、全く効果は無かった。
平安時代の永長元年(1096年)には「永長の大田楽」と呼ばれる、春から初夏に至るまで続いた田楽の巨大催事が偶発的に発生した。その熱狂はすさまじいもので、庶民だけでなく、貴族や皇族までもが踊りに参加したという。(※註釈)
平安末期の久寿元年(1154年)の今宮社御霊会では傘の上に風流な飾りの花を掲げて唄い囃した「風流のあそび」が行われたと平安時代末期に編まれた『梁塵秘抄口伝集』巻14に記されている。
平安末期以後には、今日の祇園祭祭礼で曳かれる山車(ルビ:だし)や、その際に着る衣装や、花見などの宴席で施される華美な趣向を「風流」と呼ぶようになったという。そのような風流な嗜好を好む人を風流者(ルビ:ふりゅうざ)と呼んだ。さらに風流は庶民の芸能や美意識であったが、貴族階級にも普及していった。
平安時代には怨霊信仰が盛(ルビ:さか)んとなり、(※参照:上田正昭『日本の神々』 学生社 2003年 p.77 - 78)祟り神を慰めるための鎮魂祭である「御霊会」(ルビ:ごりょうえ)が数多く催されるようになった。スサノオを祀る信仰を習合したこの時代の御霊会が、現代も続く祇園祭の起源とされる。
先の『梁塵秘抄口伝集』巻14)には、久寿元年(1154年)の今宮社御霊会で、傘の上に風流な飾りの花を掲げて、唄い囃す「風流のあそび」が行われと記されている。
・踊る農村
京都の町を離れて農村部を見ても、同じく戦国時代とはいえ、陰惨な生活に苦しんでいただけではないようだ。『月次風俗図屏風』(つきなみふうぞくずびょうぶ)(室町時代・16世紀)に描かれた田植えの風景は実に愉快で楽しそうだ。踊る早乙女の女たち、運ばれていく大量のごちそう、田植え猿楽はお囃子(ルビ:おはやし)を演奏している。春の暖かさと、農村の労働はけしてつらく苦しいものではなく、地縁で結束した共同体による神事にも似た行事として行われた。この図からも読み取れるように、この時代は町衆、~衆という、日本的な民衆が誕生して、俗の文化や、祝祭の行事や思考を成立させたのであった。
風流はこのような「風流踊り」と呼ばれた各種のイベントによって語ることができるが、風流踊りは、現代の日本で神社や町内会で行われる祝祭儀礼である「盆踊り」に通じる。
*風流傘と天蓋の章は省略
C-3 風流—古式に反発する庶民の美意識の誕生
・貴族とは異なるみやびさ
一般的に仏教において「荘厳」(ルビ:しょうげん)とは、立派な装飾を整えるイメージであるが、ここで書いてきたように、もりあげる、あげていく、いや、という、ルーチン化する以前のあげあげの思想を言う言葉とも取れる。風流傘とは、シンボルであり、よりしろとであり、神仏ののりものであり、同時に、御霊のための祭壇であり、祝祭的な芸能の装置そのものである。
それは不動の社ではなく、移動していく鉾である。貴の対峙する俗の側、あるいはその両方を結びつけるようにして成立した、日本独特の統合的な意匠であるといっていい。
俗の「荘厳」とは、立派なだけでなく、ウイットやユーモアや、偶発的な面白さなど、より多面的なものを含み、面白さや滑稽さや、いきいきとしたアクチュアリティー、エロスをともないながら、そうでありながら、グローリー、本来の「荘厳」さを棄却しようとするようなものとして定義しておきたい。
・俗とは新しさである。(尼ヶ崎P78)
風流は、当初は中国の歴史に倣い、才能豊かな人の様を表す言葉であった。その後「みやび」とよまれる言葉であった。しかし、その語の意味は、いつしか入れ替わっていったように思える。
というのも「みやび」の語源は「宮び」すなわち、貴族側の文化を表す側にあったのだが、いつしか「雅」の文字が当てられるようになった。それは美学の基準が「宮び」―ラグジュアリーか、「鄙び」(ルビ:ひな)ーいやしい、ではなく、「雅」か「俗」に移ったことに対応していると、尼ヶ崎淋は指摘している。
この「鄙び」とは、当時の言葉で田舎っぽいことをいうのだという。
さらに、この「雅」と対をなす「俗」とは、現代的なものなの、新しいものをさすのだと、尼ヶ崎は続ける。由緒がなく、歴st駅価値がないもの、といったところだろうか。
風流とはまさしく、このような、時代において、成立した価値感、流行的な、新しいものであった。ニュアンス的であって、難しいが、少なくとも、最小に書いた通り、俗の側になった美意識の風流は、奇抜であり、~~なもの、あえて書くなら、貴族のみやびを模倣しながら、どこかずれていたり、アンチテーゼ的に奇抜さを含めた、庶民の美意識であっただろう。それは貴族にしてみれば、いつもの自分たちの生活のパロディーであったり、逸脱であるから、庶民とは別の感覚で楽しめたのかも知れない。
・風流は日本の俗美術そのもの
「美術」という言葉は、明治期に西洋から輸入された概念であり造語といえよう。国際万博に出品する品のカテゴリーを書き示す段になって、これらの工芸品や、制作物をなんと呼ぶべきか、当時の日本、それまでの日本には適当な言葉がなく、ドイツ語の「クンスト」の妙訳として「美術」が当てられたという。
日本にはそれまで美術と称するべき概念がなかったという自体には驚かされるが、もしそうであるなら、美術に訳せない言葉か、現在我々が使う美術とは異なるなにかしらの言葉がなければつじつまがあわない。おそらく世界的な概念としての美術に対応できなかった、日本的な美意識、あるいは美学として、使われていた言葉のひとつが、風流であったといっていいだろう。
付け加えるなら、多くの日本美術史で、風流を紹介する書籍はけして多くはない。それは風流自体が概念であり、さらに絵画や工芸品、彫刻作品を主流として取り扱う日本の美術史において、風流やばさらが直接介在する作品といったものが、けっして多くはないし、あったとしても、たとえば「洛外洛中図絵巻」などの風景画のどこかに、関係する所作や、人物を見つけるに留まるのみであるからであろう。さらに貴族や武家といったその時代の富裕層に関連するか、同じく寺院仏閣など宗教組織が宗教的な利用などを目的として制作した絵画・彫刻などの美術品、簡単にくくるならば時代ごとのハイ・アートを中心として美術史が語られてきたためであると容易に理解出来る。
同様の理由で、そのような庶民に支持された遺物が多くはのこされていないことも理由のひとつであろう。ただし、それよりも指摘しておきたいのは、歴史を左右した支配者層と関連する人々の歴史にそって、美術史が語られているため、風流と関連する美術が紹介されていないという事実である。
江戸時代になると浮世絵や歌舞伎など民衆側に成立した美術と芸能がについての紹介と論考が急に行われるわけであるが、そのような町民文化が江戸期、および安土籾山の時代だけで急に成立したわけではなく、より古い時代から脈々と受け継がれてきた「俗の美学」が江戸期に爆発的なエネルギーで普及したと考えるのは妥当であろう。別な言い方をするなら、これまで美術史で語られてきた各時代のトピックからもそれら俗の美術を読み取ることが出来ると考えて本書は論考をおこなうものである。

日本の仏教寺院、五重塔、墓石などのデザインの基本は、ヒンドゥ教のシュワリンガに通じる
笠の形状をモチーフとする。
月次風俗図屏風(つきなみふうぞくずびょうぶ)室町時代・16世紀
公家や武家、そして庶民にいたる様々な階層の風俗を描く。右端には旧暦正月の羽根つきや毬打*だきゅう*、二番目の画面には三月の花見、左端には十二月の雪遊びなどが見える。季節や月ごとの行事を描く、伝統的なやまと絵画題である月次絵*つきなみえ*の形式を継承したもの。
能

D 婆娑羅の美意識 — 武士階級の風流と、悪党と呼ばれた畏敬異類の人々
D-1 婆娑羅登場
・サムライ・バサラ思考
婆娑羅(ルビ:ばさら)(※)とは、鎌倉末期からにわかに成立した概念で、おおむね南北朝時代(1336~1392年)の間に流行していた武家を中心か、武家を含む庶民にまで及んだ、やんちゃな美意識または思考とその風潮の総称であった。当時の流行語として用いられていて、飾りたてた華美な服装や風体を表し、または勝手気ままで遠慮がなく非常識なふるまい、または珍奇な品物などを表す言葉であった。
室町幕府が成立した年に公布された、幕府の施政方針を示した『建武式目』(ルビ:けんむしきもく)(建武3年 1336年)には、「近日婆佐羅(ルビ:ばさら)と号して、専ら過差(ルビ:かさ)を好み、綾羅錦繍(ルビ:りょうらきんしゅう)・精好銀剣(ルビ:せいごうぎんけん)・風流服飾(ルビ:ふうりゅうそうしょく)、目を驚かさざるなし、頗る(ルビ:すこぶ)物狂(ルビ:ぶっきょう)と謂(ルビ:いひ)ふべきか」(※ルビ抜き表記別記)と記されている。過差とは奢侈(ルビ:しゃし)、すなわち「必要な程度や身分を越えた贅沢」であり、綾羅錦繍―上質の素材に、刺繍を数多く施した美しい衣服や、精好銀剣ー練糸をたて糸、生糸をよこ糸にして織った絹織物と、神社に奉納されるような銀(ルビ:しろがね)の太刀(ルビ:たち)など、風流服飾ー数奇(ルビ:すき)な趣向を凝らして飾り立てた衣装を身に着けていて、婆娑羅というが、これは物狂―とんでもないし、あきれるほど異常であると「婆佐羅」を説明している。要はそんなものはとんでもないというのである。
婆娑羅の語源ははっきりしない。十二神将像の塑像のひとつ伐折羅大将、あの髪を逆立てた忿怒の顔が印象的な奈良新薬師寺の憤怒の表情の闘神から来ているのではないかと言われている。そうであれば、サンスクリット語のvajra(バジラ)から転訛(ルビ:てんか)した言葉だ。それはなにものであろうと打ち破る強さをもつブラックダイヤモンドを意味する。それは金剛力士像の金剛、仏敵を退散させる武器金剛杵(ルビ:こんごうしょ)のなにものにも負けない、もっとも強力なものを意味するという説が有力である。(※参照:尼ヶ崎淋『いきと風流―日本人の生き方と生活の美学』P129)
このサンスクリット語のvajra(バジラ)が伐折羅となり、のちの平安時代に、雅楽や舞楽の分野で、伝統的な奏法ではない自由な奏法を婆娑羅と呼ぶようになり、やがて「常識を打ち破るような強さ」というものへと変化していった。
またこれとは別な説として、「婆娑」という「舞う人の衣装の袖(ルビ:そで)が美しくひるがえるさま、または舞いめぐる様」を表す言葉が「さまよいめぐるさま、徘徊するさま」へと転じたもので、南北朝の対立の時代の京都で、路頭を組んで傍若無人に派手なかっこで街を徘徊する足利利方の武士たちの様子を、本人たちが「婆娑羅」と自称したのではないかと、遠藤基郎による推察がある。(※参照:遠藤基郎「婆娑羅」から考える」『東京大学史料編纂所編『日本史の森をゆく - 史料が語るとっておきの42話』(中公新書)P17)
D-2 畏形異類の人々
・悪党
語源とその時代的変化はあるにしても、もともと婆娑羅と称されていたのは、鎌倉時代末期以降に登場する体制に反逆する悪党と呼ばれた人々の形式や常識から逸脱して奔放で人目を引く振る舞いや、派手な姿格好で身分の上下に遠慮せず好き勝手に振舞う者達を指す(※参照:ウィキペディア)言葉として使われ、やがて、そのような人々や振る舞いを表す形容詞となってこの意味で定着したという。
悪党とはなにか。を説明するためには、奈良時代から始まる荘園制度から紐解かなければならない。
日本史に繰り返し登場する荘園とは公的支配を受けないか、公的な支配を制限可能な私的所有の土地である。
7世紀に入ると官僚制度、地方制度、法令制度などの整備が徐々に進んでいき、
各々の豪族が土地と民衆を直接支配していた土地と住民の支配は、奈良時代になって否定され、中央政府による統一的な土地・民衆支配が実現した。
奈良時代の初期頃から、人口増加と財政需要に伴い、大規模な開墾計画が策定された。(開墾した農地は、期限付きで私有が認められたが、期限が到来するとせっかくの墾田も収公されてしまうため開墾は下火となった。)
そこで政府は新たな開墾推進策として、墾田の永年私有を認める墾田永年私財法を発布した。そのため、資本を持つ中央貴族や大寺社・地方の富豪たちが活発に開墾を行い、大規模な私有土地が出現することとなった。これが荘園の始まりであった。墾田は私有できたが、収穫の中から田租の納入が義務着けられた。いわゆる年貢制度の萌芽である。
奈良時代に始まった荘園制度は体制や支配体勢の変化を繰り返しながら、平安、鎌倉へと受け継がれていった。室町時代にも荘園は存続していたが、中央貴族・寺社・武士・在地領主などの権利が複雑にからみあう状況が生まれていて、自立的に発生した村落=惣村による自治も出現するようになり、荘園は緩やかに解体が始まった。さらに戦国時代になると、武力で自らの支配地域を確立していった戦国大名たちによって、それまでの土地の権利関係が解消され、支配地域が家臣や寺社に分け与えてしまい荘園制度は徐々に解体していった。
・悪党の登場~現在も使われる悪党という言葉は荘園制度と深く結びつく
荘園制度や、官僚制度、地方制度、法令制度などの整備が徐々に行われ始めた7世紀の、『続日本紀』(716年)悪党の語が史料として最初に登場するが、12世紀後半になると、荘園・公領を外部から脅かした者を指す言葉として使われるようになり、(※参照:『無縁・公界・楽』、網野善彦(平凡社「平凡社ライブラリ」1996年)やがて鎌倉幕府によって圧迫・禁止の対象となった武装集団を指す言葉として定着する。
その多くは貨幣経済の発展や、前述の荘園公領制度の成立と変化といった社会の変化に対応できず、落ちこぼれていった武士と遍歴して業を営む非農業民など、幕府や天皇の支配体系の外部に生きる漂泊的な人々であった。(※出典:株式会社平凡社百科事典マイペディア)それ以外では、蝦夷と呼ばれた遠方の人々や、海賊行為を行う海民や、流浪の芸能民、僧侶なども悪党とされていた。つまり悪党とは荘園に代表される支配体系の外部にいた人々につけられた呼称であった。そのような漂泊(エグザイル)的な生活を生業とする人々は、支配体系に属していないことを示すために、自ら奇抜な服装をしていた。すなわち「異形の者」たちであった。(※参照:網野善彦『異形の王権』P00)
・異形異類
この自ら奇抜な服装をした異形と称される者とはなにか。
南北朝時代から室町時代にかけて実際に製作された「融通念仏緑起絵巻」(ルビ:ゆうずうねんぶつえんぎえまき)(※図)は、平安時代後期に融通念仏宗をおこした良忍(ルビ:りょうにん)(1073~1132年)の事績と、念仏の功徳を説く説話を紹介する絵巻物であるが、そこに奇抜な服装をした異形の者たちが描かれている。(江戸時代に「非人」などと呼ばれて被差別の対象となった人々であったが、中世においては、人と異界の狭間に暮らす「人ならぬ存在」であったと網野善彦は書いている。 (※参照:網野善彦『異形の王権』ページ数はあとで記入)
また1348年(正平3∥貞和4)ころに成立した播磨国の地誌『峯相記』(ルビ:みねあいき)には、播磨国の悪党についての記述が残されていて、「柿色の帷子(ルビ:かたびら)を着て,笠を被り,面を覆い,飛礫(ルビ:つぶて)など独特の武器を使用して奔放な活動をした」とある。
『峯相記』は周知の通り、正安・乾元のころの悪党の姿を、柿帷(ルビ:かきかたびら)に六方笠(ルビ:ろっぽうがさ)、恐らく蓬髪(ルビ:ほうはつ)で鳥帽子(ルビ:えぼし)・袴(ルビ:はかま)を着けず、覆面をした、「人倫ニ異ナ」る「異類異形」として描き出す。〈中略〉(これが「非人」の衣装に通じていることは、別にのべたが、)正中・嘉暦のころ、「𠮷キ馬ニ乗リ列レリ、五十騎・百騎打ツゞキ、馬引(ルビ:うまびき)・唐櫃(ルビ:からと)・弓箭(ルビ:きゅうせん)・兵具ノ類ヒ、金銀ヲチリバメ、鎧・腹巻テリカガヤク計也」といわれ、「礫(ルビ:つぶて)ヲナゲ」撮棒(ルビ:さいぼう)を駆使しつつ縦横に活躍する「有徳」な悪党の姿も、また綾羅綿繍(ルビ:りょうらきんしゅう)を身にまとう放免―「非人」の衣装にその源流を持つことは明かである。まさしくこれこそ、柿帷・蓑笠(ルビ:みのかさ)と表裏をなす「婆娑羅」の風にほかならない。「天下ノ耳目ヲ驚」かしたこうした悪党たちの生命力の噴出する中で、鎌倉幕府が倒れ、建武新政権、「二条河原落書」にみられるように「婆娑羅」の風潮が世を風靡(ルビ:ふうび)したことは、もはやここにのべるまでもなかろう。(※引用:網野善彦『異形の王権』P14)
この者達は博奕(ルビ:ばくち)や盗みを行い、荘園などで紛争がおこると、賄賂をとって加担するといった活動を行っていた。(※参照:平凡社世界大百科事典 第2版)
網野善彦(ルビ:あみのよしひこ)は、これらの「悪党」は鎌倉時代後半から急速な成長を遂げていく日本国内の流通経済・資本経済の担う役割を担うものでもあったと書いている。
後醍醐天皇は元弘の乱で鎌倉幕府を倒して建武新政を実施したのち、建武の乱で足利尊氏に敗れ、南朝政権(吉野朝廷)を樹立した。その後は南北朝の内乱が勃発して尊氏の室町幕府が擁立した北朝との間で争いを続けた。この戦乱の時代に後醍醐天皇の呼びかけに応え挙兵したのは、出自が悪党的な荘官武士と推測された楠木正成をはじめとする、非御家人や、寺院勢力などの、体制からはみ出した連中であったとされる。
これら異形のもの、悪党武士など体制側に属さない、反目する「悪党」と呼ばれた人々が、体制に抵抗して、独自の文化や体勢を独尊的に成立させようという「悪党的精神」によって、成立した逸脱した身なりや振る舞いが「婆娑羅」という言葉と深く結びつきを持つようになったのだ。
事前に結論を書くと、第一に婆娑羅とは本書が問う畏怖畏崇(と、それを模倣しようとした武士階級)の美意識であり、風流はもちろん、後述するかぶき者や、 江戸時代のイキ、伊達、さらにパンクやヤンキーと親和性をもつ風潮・概念である。
第二に婆娑羅とは武士版の風流、すなわち民衆の間にひろまっていた風流を武士がどのように自分たちの活動や美意識に繁栄させたものであって、武士における豪奢さや畏敬の美意識であった。
第三に婆娑羅とは服装や装飾、住環境など生活スタイルを含む美術であるが、それは演劇的であり、パフォーマンス的な性質を強くもっている。
第四にあげなければならないのは、この婆娑羅を美術として捉えるためには、絵画や彫刻などといったものだけで捉えるよりも、むしろキュレーション的行為、現代的美術の範囲でとらえるべき美術行為である。
D-3 婆娑羅大名
・やんちゃな頂場持ち
室町幕府が終わる1370年ころまでに成立したと考えられる、南北朝時代を描く歴史文学「太平記」には「佐々木佐渡判官入道導(道)誉が一族若党供、例の婆娑羅に風流を尽して」と書かれている。この一文に登場する近江国守護大名の佐々木道誉(ルビ:ささきどうよ)(1296年または1306年~1373年)や、源氏足利将軍執事で守護大名だった高師直(ルビ:こう のもろなお)(?~1351年)、美濃国守護大名の土岐頼遠(ルビ:ときよりとお)(不明~1342年)などの言動が婆娑羅的であったと記されている。彼らはのちに「ばさら大名」と呼ばれた。(参照:新井孝重「小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)」)
・佐々木道誉
婆娑羅大名として知られる佐々木 道誉(ルビ:ささきどうよ)(1296年~1373年、1306年生まれとする説もある)は、鎌倉時代末期から南北朝時代にかけての武将、守護大名で、若狭・近江・出雲・上総・飛騨・摂津国の守護(軍事指揮官・行政官)を勤めた。
『太平記』には権威を嘲笑して、婆娑羅な振舞いを繰り返した佐々木導誉の逸話が数多く書かれている。
この頃とりわけ時代の波に乗って、豪華さで人の目を驚かせていたのが佐々木道誉だった。ある日彼の一族と若党がいつものように「ばさらに風流を尽くして」東山で鷹狩りをし、帰路たまたま妙法院の前を通りかかったとき、紅葉の枝がみごとなのでこれを従者に折り取らせた。
どうやら一族と若衆とあるが、金にものを言わせて華麗で奇抜な趣向をかけてといったところのようだ。
話は続く。紅葉の枝を勝手に折っている導誉たちを見つけた妙法院の坊官が、やめるよう制止するのだが、導誉たちは一向に聞き入れず、それどころかふざけて笑いながら、より大きな枝を折ってしまう。この妙法院とは皇族の子弟が門主(住職)を勤める本山比叡山延暦寺の支配下にある寺で、泊まっていた延暦寺の山法師(武装した僧兵)が大勢出てきて、小競り合いとなり、道誉たちはたたき出されてしまう。
これを聞いた道誉は激昂して、自ら三百騎もの兵を率いて妙法院に押しかけ、火を放つ。この時の門主(住職)を勤めていた光巌天皇の弟亮性(ルビ:りょうしょう)法親王も裸足で逃げ出した。道誉の息子は捕まえた若宮(幼い皇子)に乱暴をはたらく。この事件で京中は大騒ぎになった。
要は天皇や仏教寺院の権威や権力など怖れず、やりたい放題をやってしまう。このような佐々木道誉の生き様や態度を、本人たちは誇らしげに婆娑羅と称した。その行いはアウトローであり、任侠的といえるであろう。幕府の権威も失態していて、皇族が南朝と北朝に別れが対立して争う南北朝時代に、いったいなにが権威であって、従うべきか、すでに失墜した旧制度など虚像でしかなく、なにより信用に値するのは即時性ある圧倒的な暴力や威圧的な恫喝の様ー様態であるといった、ヤクザなどの暴力集団が得意とする喧嘩上等のいかつさと、その実力行使の様相がこの事件から見て取れる。それは後の戦国時代の下克上的精神とも通じている。
もうひとつ読み取れるのは、道誉(たちの)遊興的な嗜好であろう。この事件は鷹狩りから始まり、寺の者を笑いからかい喧嘩に発展するが、派兵して放火までした後に、わざわざ皇子をいたぶるという、「バカ騒ぎ」を好む不良行為少年や暴力団の末端組員に見られた暴力行為を楽しんでいる様子が思い浮かぶ。
一方では反骨的な反体制主義を掲げるヒーロー的な性格を見せているようであるが、その分刹那的で自暴的な性質と反社会的暴力勢力の様相がよみとれる。
『太平記』のこの事件は続く。道誉たち一族はこの一件で(当然だが)処罰されて京都から上総(千葉)へと流罪になる。
この時道誉は三百余騎もの若党(年が若い郎党)を従わせ、さながらパレードのような行列で道中を行う。全員が靫(ルビ:うつぼ)(腰につける矢を入れる道具)に猿皮をあしらい、腰当てにも猿皮をあつらい、手には鶯(ルビ:うぐいす)のかごを持たせていた。先々の宿ではその人数で酒肴に遊女を呼んでの宴会を開いた。猿皮は高級品であった。それを三百人もの若造が身に付けているというのは豪奢の極みであっただろう。そして猿は比叡山において神の使いとされる聖獣であった。その猿を大量に殺して皮を剥いで腰当てに使うというのは、延暦寺に対する挑発であった。さてこの数奇なる三百人もの列隊が手にしていた鶯だが、この頃に鶯合わせという鶯の声の美しさを競う遊びが流行っていたためだという。これを文雅の素養を持ち合わせた武士たちと取るのも可能だが、はやりのいけてるキーホルダーをみなもっていたという呈で捉えるのも可能かもしれない。
このような道誉の様が婆娑羅と呼ばれた。従来の身分秩序や社会的規約に縛られず、権威を軽んじて嘲笑・反撥し、武闘派で実力主義的であり、華美な服装を好み、奢侈で派手な振る舞いを、あえて高らかに誇示する。そのような精神性や美意識が
婆娑羅であった。繰り返しとなるが、このような武士の嗜好や倫理感が、後に訪れる戦国時代における下克上の要因となっていく。
これだけの事件でおとがめを受けた道誉であったが、翌年には北朝軍との戦いに参戦して、その後シレッと京都に戻ってしまう。南北朝時代という軍事的素養やキャリアがなにより高く評価されてしまうこの時代に、力をもった武将である道誉に厳しく対処できないという時の政権側の事情も垣間見れるが、なにより、そのような時代であったからこそ婆娑羅的思考が生まれ、婆娑羅の武将が成立したのである。
・桜源郷 婆娑羅のサイトスペシスフィック・インスタレーション
花見の風習が広く庶民に広まっていったのは江戸時代であったが、その始まりは奈良時代の貴族行事が起源といわれる。当初は中国から伝来した梅を鑑賞していたが、平安時代に桜に代わっていった。史記として記録が残る花見の初出は『日本後紀』で、嵯峨天皇が812年の3月28日(平安時代、弘仁3年2月12日)に神泉苑で「花宴の節(ルビ:せち)」を催したと記されている。この日付から花は桜であろう。この頃から貴族の間で花見は急速に広まり、鎌倉・室町時代には武士階級にも花見の風習が広がった。(※参照:日本の食文化と偉人たち豊臣秀吉 太閤秀吉が演出した空前絶後の醍醐の花見 キリン食生活文化研究所)
さて野外で開かれる花見をいかに豪奢なものとして感嘆させるか。
1366年の春、佐々木道誉は税を尽くした盛大な花見を大原野(おおはらの)(京都市西京区)で催した。その際の記録が『太平記』(ページ00)に記されている。
花見は大原野の山をまるごと会場として、寺の高襴(建物の縁)は、金糸などで紋様を織り出した金襴豪華な織物で覆われていて、擬玉珠(玉や真珠を摸したデコレーション)に金箔が貼ってある。毛氈(ルビ:もうせん)と呼ばれた羊毛などを原料として作られた中国の高級敷物(カーペット)を引き詰めてある。その上にチリ積もっている桜がまるで雪のように見える。踏むと冷たく、歩くと草履が香る。石の階段を上まで登ると、泉から湧き出た水が竹の管を伝わり、石の鼎(ルビ:かなえ)(古代中国で使われた、三本足の鉄のかま)にはお茶のためのお湯が沸いている。春を感じながらお茶を飲むとまるで俗世を離れ仙境(ルビ:せんきょう)にいるような清々しい気分になる。(中略) ここから遠くを見渡すと、山や川があって、絵のように美しい。一歩ずつ感嘆しながら本堂まで登っていくと、その庭には桜の巨木が四本あるのだけれど、それぞれが巨大な真鍮(ルビ:しんちゅう)の花瓶で囲んであって、桜の木が生け花の花のように見立ててある。一斤もの名香を惜しみなく香炉で焚いて、四方すべてにその芳しい香りが漂い。幕が張られた椅子が並べられ、「百味の珍禅」と書かれるほど豪華な料理が振る舞われる。当時流行っていた「闘茶」という飲んだお茶の銘柄を当てるという、金持ちの凋落的遊戯が行われたが、その勝者に贈呈される商品が山のように積まれていた。猿楽師が舞い、白拍子(ルビ:しらびょうし)と遊女が唄うと、参加していた金持ち連中がみな着ていた豪勢な衣装を次々に脱いで投げ与えていた。その宴は深夜まで続いて、帰路を行く人々の松明(ルビ:たいまつ)のあかりが夜空を照らすほどで、螺鈿(ルビ:らでん)で飾られた豪華な牛車の音が轟(ルビ:とどろ)き、馬の轡(ルビ:くつわ)や、大声で笑う人々の声が響き渡る様は、まるで深夜に京都の街を行く百鬼夜行のパレードのようであった。
さて、いったいどれだけの金をつぎ込んで、このようなイベントを成立させたのか、そのような無粋な心配はやめておこう。
この花見は京中で噂になったのはいうまでもない。
なにより見事なのは艶やかな空間に仕立てた演出であるが、この花見が場所の特性を活かしたサイトスペシフィック型の構造をもち、移動しながら楽しむ体験型のインスタレーション的な経験に訴求する現代の美術作品のように演出されている。足で踏みしめて知る桜の冷たさという皮膚感覚、草履に纏わり付く香や、野外のとてつもない広さに芳しい臭いを漂わせるお香、目で見る豪奢な飾りや、流れるせせらぎの水、巨大な生け花に見立てた桜の木、遠く遠景の風景までを取り入れた借景的な演出効果は造園家や建築家の美意識といえるであろう。エンターテイメントとして美しい女性たちの歌や踊りと優美な猿楽が演じられる。贅を尽くした料理に美酒が振る舞われ、アトラクションとして開催されたお茶のゲームで与えられる豪華な宝の山までがあるのだ。
クラブ・イベントと同じく、こういうのは金を積むだけでは成立しない。遊び人でありながら、それぞれの芸事を認めて尊重するパトロン的な信頼や友好関係がなければ、とってつけたようなものになってしまう。こういうや企画や演出は、育ちがよくて知的素養があっても貴族階級にはできない相談だ。
道誉のようにとんでもない金持ちではあるが、遊女や白拍子ともつきあえる俗の側と表裏一体の関係性をもてるような人間でなければ実現不可能なのだ。そして、いったい幾らの金をかけたのだろうと野暮な意識が働くほど、金を惜しげも無く使う。
たった一日の催しのために舶来の高価な品々を使い、用意した品々や着ていた高価な服を芸人たち身分がない者たちに惜しげも無く投げ与える。豪快であり、破格の大盤振る舞い。際限のなさが、婆娑羅という言葉と、佐々木道元の名を後生にまで語り継がせる。
アバンギャルドや、バブリーなど、どれだけ形容の言葉や、代替のイメージを付け加えても、言い表せきらない、派手さ、豪快さ、ばからしさが、狂乱的な美学と、それを実行してしまう思考とコネクション、人を感嘆させるだけのセンスや演出力といったもののすべてが、集結して、この従来通りの花見と称した婆娑羅的祝祭空間が成立した。
ところでこの道誉の婆娑羅花見には、もう一つの物語があった。この歴史的婆娑羅イベントと同じ日に政敵である斯波高経が花見を開いていたのだが、招待された道誉は参加すると返事をしておいて、わざと勘違いして、同日にこの花見を行ったのである。都の話題は道誉ばかりで、将軍御所で開かれた高経の花見などだれも話題にしなかった。高経の顔を見事につぶすのも、この花見のもうひとつの目的だった。 (※参照:尼ヶ崎淋『いきと風流―日本人の生き方と生活の美学』P131) https://www.guidoor.jp/media/basara-doyo-sasaki/
D-4 婆娑羅の風流をキューレーションとして読み解く あるいは成金の美学について
・噂となる榮誉
これらのような「太平記」におけるばさら大名たちの言動や振る舞いの記録は残っているが、婆娑羅という風潮とその美術がどのようなものだったのかは、視覚的な資料としての記録はほとんど残っていない。そうでありながら、彼ら婆娑羅なる武士の存在が21世紀にいたるまで伝えられ、興味をひくのか?それは興味深い。
いずれにせよ、婆娑羅が、この時代の武士層の一部に支持された特異な美意識や風潮であったのは変わりないが、残されている史料は多くはない。それらは当時の絵画に描かれているそれらしきものや、史料に残る婆娑羅と呼ばれた人々の振るまいや記録から読み解いていくしかない。
このようなもともとの出目が悪党といわれる武士とは異なる佐々木道元のような御家人から登場した婆娑羅大名は、おそらく南北朝時代という、幕府の支配がゆらいでいた時代に登場した内部勢力であり、同時に前述した風流的武士であった。
・成金最高!
成金嗜好とよばれるものは、おおむねバッドテイスト(悪趣味)であったり、度を超えて、デカかったり、きらびやかすぎるものを指す場合が多いようだが、ここにあげた婆娑羅大名の逸話が少なからずそのような印象をもつものであった。
「成金」という語は、もとは貧乏だったのが急に金持に転じた人への称賛や愛慕を込めて用いられてきた。将棋で敵陣に入って金将の資格を得た歩などの駒などに喩えた言葉である。江戸時代後期から使われ始めたが。第一次世界大戦頃の大戦景気にのって急に富裕層に転じた者を指して使われ一般に広まった。
成金とは日本の大正期に始まったものではなく、古くからなにかしらの悪運に恵まれて富をなした人間に共通して伺える気質のようだ。
古代ギリシャの時代にアリストテレスは、成金の性質について次のように書いている。
1、その性格を一言で言えば、幸運に恵まれた愚か者の性格である。2、良いものをすべて持っている気になっているために、傲岸不遜である。3,贅沢を見せびらかす。4,金がすべての評価の基準になっている。5,自分好みのものに囲まれて生活しているため、他人が別の好みを持っていることを忘れる。(これは現代のオタク的特性や、ネトウヨと呼ばれる人々にも通じるように思う。)6,自分が官職につくべき人間だと考える。7,金持ちであることの心得がまだできていないために、金持ちであることにつきものの欠点を古くからの金持ちよりもっと悪い形で持っている。7、成金が不正行為に手を染めるのは、悪意からではなく、傲慢や抑制力のなさからである。(※引用:アリストテレス『弁論術』「第二巻第十六章―運による性格(二) 富・金持の性格/成金と古くからの金持/金持の不正」戸塚 七郎 (翻訳))
しかし佐々木道誉の場合はどうか。寺に押しかけた件は、血の気が多いドキュン系クレーマーにもほどがあるし、暴力的であるし、どこか、血なまぐさい、他の侍たちの物語に、猿の皮がかぶせられたような、悪趣味として、捉えることもできる。
だが、花見の件は、いわゆる成金と呼ばれるものとは明らかに異なる。なにかしら、見るものを、陶酔させ、あっと驚かせて、さらに当事者である本人を越えて、伝承されるような、ある種の作為的な意図が読み取れる。それを美術的と呼んでもいい。あるいはイベント・デザイン的思考や、コンセプト重視の体感型アミューズメントのようなものを作り出したといってもいいのではないだろうか。
ここで考えて頂きたいのは、「成金趣味」と切り捨てられてしまうだけの、ある種の美意識や、行為を、改めて、捉え直してみるなら、ベルサイユ宮殿や、シュバルの建造物、あるいはセレブの邸宅なども、まったく異なる捉え方もできるといった価値感についてである。
現在の我々が知る公共的—民主的といってもいい賛美眼主義とは異なる「もうひとつ美意識」や「新しい美学」を思考するためには、これら、俗の側から、たちあがった美術を再考する必要があるのではないか。
ここであげた、婆娑羅のキューレーションもそのひとつに他ならない。
D-5 婆娑羅再考
・婆娑羅まとめ
婆娑羅の絢爛豪華な装いと振る舞いは、王朝依頼の貴族文化を出発点とするが、その根底には風流の美学があり、けっして田舎の武家にできるものではない。彼らの豪奢絢爛で型破りで人を驚かせる行いには、斬新さに通じる新しい素養と教養が必用不可欠で、さらにその演出が重要であった。
その流れは数奇的な、それこそポスト婆娑羅と呼ぶべき新しい芸術や文化、後述する戦国時代の武将たちの振る舞いや、のちの江戸庶民の美意識や芸術にも多くの影響をあたえている。
婆娑羅とは、本講が問う畏怖畏崇の美意識そのものである。
第一に、風流はもちろん、後述するかぶき者や、 江戸時代のイキ、伊達、さらにパンクやヤンキーと親和性をもつ風潮・概念である。
第二に婆娑羅とは武士版の風流、すなわち民衆の間にひろまっていた風流を武士がどのように自分たちの活動や美意識に繁栄させたものであって、武士における豪奢さや畏敬の美意識であった。
第三に婆娑羅とは服装や装飾、住環境など生活スタイルを含む美術であるが、それは演劇的でパフォーマンス的な性質を強くもっている。
第四としてあげなければならないのは、この婆娑羅を美術として捉えるためには、絵画や彫刻などといったものだけで捉えるよりも、むしろキュレーション的行為、現代的美術の範囲でとらえるべき美術行為である。 http://www.kagakueizo.org/create/yoneproduction/267/
五番目として指摘しておきたいのが、そのコンセプチュアルな思考についてである。 おそらくそれは今私たちが知るところ以上に、武士的な思考であったのではないだろうか。サムライという死を意識した行き方は、どのように我を世に刻むか、生き様というような(日本人が好きそうな)言葉をどう見せつけるか、歴史に刻印するかが、重要であっただろう。いさぎよさ、つまり、コンセプチャアルな意識と、そのような芸術性が、あったのではないかと、推測する。
婆娑羅誕生の経緯、荘園制度、悪党という名称はともかく、荘園制度、年貢、国(石)という褒美の制度が、破綻、崩壊、矛盾によりる、サムライや、民衆に対する、セーフティーネットのなさ、が作り出した時代の空気と、社会問題が、この時代の美意識に刻み込まれている。
そのような思考を共有していたのがm婆娑羅と社会に属さない人々—非人や、遊女や、悪党とよばれた人々であった。かららの刹那な世界観がこのような美意識を成立させた。
・継承される風流と婆娑羅
戦国時代になると、佐々木たち先人の伝説をもとに、数奇、たわけ者な振る舞いをおこなった武士たちが登場する。かぶくという言葉とともに表れる「かぶきもの」である。歌舞伎の語源となる人々である。
婆娑羅を含む、この時代に発生した美意識は、どれもが「風流」を源流とする、または風流の中にふくまれる現象と捉えることもできるだろう。
繰り返しとなるが、婆娑羅を成立させた「風流」という俗の美意識、日本独自の芸術運動は、その後の日本美術の多くに通底する、もっとも日本的な美意識であり、その発生は、日本美術における歴史的大事件であった。
サイトスペシフィック・アート(英: Site-specific Art)
特定の場所に存在するために制作された美術作品および経過のことをさす。一般に、美術作品を設計し制作する間、制作者は場所を考慮する。
屋外のサイトスペシフィック・アートにおいては、時には、恒久的に設置された彫刻(環境アート)などとも結びつきが深く、造園またはガーデンデザイン的な仕事(ランドスケープ・アーキテクチャー)を含む。また、屋内のサイトスペシフィック・アートの作品においては、建物の設計者と連携して制作されることもある。(引用:ウイキペディア)
昭和のバブル、中世から変わらない日本的祝祭性 あるいは風流の流れといっていいムーブメント。
E 中世における恐れの信仰と、民衆の風流により始動した日本的俗の美学
密教の不動明王や闘神にみられる威嚇する仏像美術。
浄土教と穢土思想の挾間で成立した恐れの美術。
庶民たちの間で開花して、絶えることなく続いている風流の美意識。
婆娑羅における刹那なる武士と異類異形の人々の美意識。
この4つを柱として、日本の中世に萌芽した、独特の怖い物を崇め、また怖れ、さらに祝祭的な装いや祭礼を、日常へと持ち込んでいった庶民たちの美意識について検証した。
風流はは歌舞伎や盆踊りなど、日本的といわれる儀礼や芸能の根源である。
・後生へと受け継がれた日本の美意識 — 次回予告
これらの得意な美術的活動を、中世の歴史の中に内包した日本は、その勢いを消すことなく、戦国時代後の、安土・桃山を経て江戸時代へと受け継いでいった。
歌舞伎や、浮世絵など、世界的にも、他に類を見ない民衆の文化が、江戸の街で成立した。
その得意な文化は、外的な侵入を許さない、治安と、徳川幕府という300年も続く安定政権のゆりかごの中で熟成されていく。
イキや、粋、いなせ、などの美学、あるいは、かぶき者など、ストリートを闊歩した
無頼の人々の文化や、風習や、思考へと受け継がれていった。
次回は、近代—戦国時代後のしらけムード、世界的に類を見ない江戸庶民の遊興文化、安土桃山のしらけムードとバブル感、かぶき者からイキの美学へ—出口なしの若者パワーと美意識、江戸庶民文化におけるポップアート — 歌舞伎と錦絵などを検証して、
本講がテーマとする日本独自の美意識の成立と、その歴史的関係性について、引き続き論考を行う。
以上 42200文字